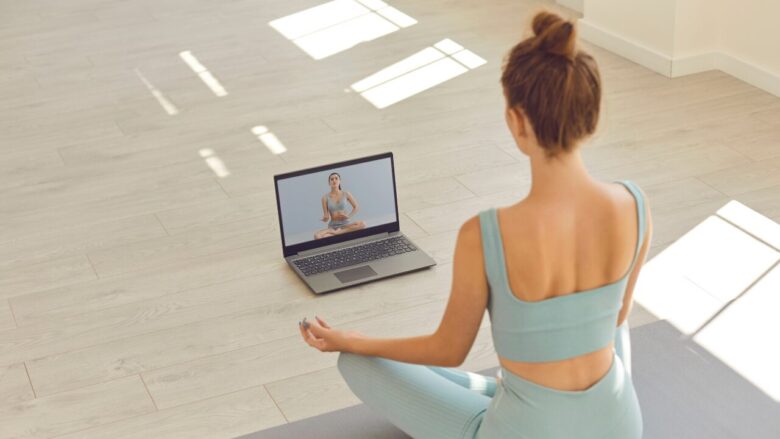最終更新日:2025.11.18
「理由はわからないけれど、なんだか心が重い」
そんな日が続くと、自分でもどうすればいいのかわからなくなります。
仕事でも家でも気を遣い、人の機嫌を察してばかり。
誰かのひと言に傷ついたり、SNSの投稿に心がざわついたり。
平気なふりをしても、夜になると小さな不安が胸の奥で膨らんでいく――。
「もやもやする気持ち」は、決して特別なものではありません。
それは、心が疲れたときに出す静かなSOSです。
この記事では、そんな気持ちをやさしく整えるための「もやもやする気持ちの解消法」を、心理的な原因と具体的なセルフケアの両面から紹介します。
感情を押し込めてがんばりすぎてしまうあなたへ。
言葉にならない心の重さを少しずつ軽くし、「それでも大丈夫」と思える時間を一緒に見つけていきましょう。
【体験談】否定されたひと言が、何日も心に残ってしまう私の場合

他人から否定されていると感じると、もやもやが何日も晴れず、心がずっと重いままになることがあります。
たとえば、私が作った計画に対して、上司から「突っ込みどころ満載」と言われたとき。
その瞬間、胸の奥に冷たいものが落ちたような感覚がして、「私のやり方は全部間違っていたのかな」「努力が足りなかったのかな」と、様々な思いが一気に押し寄せました。
仕事をしていれば否定される場面があることは、頭では理解しているつもりです。
問題は、相手の伝え方があまりにもドライだったり、気遣いのない言葉が唐突に突き刺さること。
そのひと言が、人一倍心に残ってしまうのです。
否定された瞬間だけでは終わらず、その言葉が頭の中でぐるぐると回り続け、気づけば他の業務に集中できない状態になります。
目の前の仕事に意識が向かず、焦りから新しいミスまで引き起こしてしまう。
一つの否定が、「ミス → 落ち込み → 自己否定 → さらに集中できない」という“二次災害”につながってしまうこともありました。
「伝え方が上手な人ばかりじゃない」。
これは、社会に出てから強く感じた現実です。
むしろ、指摘の仕方が雑だったり、こちらの意図を汲む前に切り捨てるような言い方をする人の方が多いと感じることさえあります。
落ち込むだけでなく、心の奥でイラッとしたり、悔しさや悲しさが入り交じって感情が混乱することもあります。
だからこそ、もやもやした気持ちを抱え続けないための対処法を知らないと、精神衛生上本当につらくなってしまいます。
私はそのことを、何度も心が疲れ果ててしまった経験から、痛いほど理解するようになりました。
否定されたひと言に心が支配されないためには、その都度感情を整理する方法や、自分の心を守る小さな習慣が必要なのだと、今では強く感じています。
もやもやする時の心理的な原因と特徴を知る

「なんでこんなに気持ちが落ち着かないんだろう」
そんなふうに感じるとき、私たちはつい自分を責めてしまいます。
でも、もやもやする気持ちにはちゃんと理由があります。
心の中では、言葉にならないストレスや感情が静かに積み重なっています。
それが限界に近づいたとき、心が「もう少しやさしくして」とサインを出しているのです。
ここでは、もやもやを引き起こす心理的な背景をやさしく整理していきましょう。
1. 自己否定・我慢・気遣いが積み重なると起こる心の反応
もやもやする気持ちの大きな原因のひとつが、「我慢」や「自己否定」の積み重ねです。
「もっと頑張らなきゃ」
「これくらい我慢しないと」
「私が悪いのかもしれない」
そんな言葉を、無意識のうちに心の中で繰り返していませんか。
人に気を遣うことが多い人ほど、自分の本音を押し込めてしまいがちです。
その結果、心は息を詰めるように苦しくなり、行き場を失った感情が“もやもや”として現れます。
たとえば、職場で誰かのミスをフォローしても感謝されなかったとき。
「なんで私ばかり」と思うのに、笑顔でやり過ごしてしまう。
そんな小さな我慢が積み重なると、心の中に小石のような違和感がたまっていくのです。
我慢を続けるよりも、「つらいな」「疲れたな」と正直に感じること。
それが、心を守る第一歩になります。
2. 「他人の感情を受け取ってしまう」共感疲れのサイン
HSP(繊細な気質)の人は、まわりの人の感情を敏感に感じ取ります。
そのため、自分の感情と他人の感情の境界が曖昧になりやすく、いつのまにか“共感疲れ”を起こしてしまうことがあります。
たとえば、職場の空気がピリッとしているだけで、自分のせいのように感じてしまう。
友人が落ち込んでいると、自分まで沈んでしまう。
そんな優しさの裏には、「誰かのために頑張りすぎている自分」がいます。
共感する力はあなたの素敵な長所です。
けれど、まわりのすべてを背負う必要はありません。
「これは相手の感情」「これは自分の気持ち」と、少しずつ境界線を意識することで、心の負担はやわらいでいきます。
3. 情報過多・刺激過多が心の静けさを奪う仕組み
現代社会では、スマホを開けばあらゆる情報が流れ込んできます。
ニュース、SNS、メール、広告。私たちの心は、知らないうちに情報の洪水の中で疲弊しています。
特に繊細な人は、たくさんの情報を「自分のことのように」感じやすい傾向があります。
悲しいニュースを見て落ち込んだり、他人の投稿を見て焦ったり。
情報を受け取りすぎると、心のスペースがどんどん狭くなっていくのです。
もやもやを感じたら、
- スマホを閉じて窓の外を見る
- 静かな音楽を流す
- 5分だけ深呼吸する
そんな小さな習慣でも、心のざわめきは少しずつ落ち着いていきます。
4. 原因がわからない不安は「心のSOS」である
原因がはっきりしないのに、なんとなく落ち着かない。
そんなときこそ、心は「もう限界かもしれない」と訴えています。
不安を感じること自体は、悪いことではありません。
むしろ、心が自分を守ろうとしている自然な反応です。
たとえば、長い間ずっと緊張していたり、頑張り続けていたりすると、心のエネルギーが消耗していきます。
その結果、「もう頑張れない」と感じる前に、心が“もやもや”という形で警告を出してくれるのです。
不安を無理に押し込めず、「いま、少し疲れているんだな」と受け止めること。
それだけでも、心は少しずつやわらぎます。
もやもやする気持ちは、弱さではなく心のやさしい防衛反応です。
自己否定、共感疲れ、情報の多さ――どれも、心が疲れた証拠。
大切なのは、自分を責めることではなく、「よく頑張ってきたね」と労わることです。
もやもやを理解することは、心を整える第一歩。
そして、feeveraが届けたいのは、そんな自分にやさしくする時間です。
もやもやする気持ちの解消法5選|今すぐ心を軽くする習慣

気持ちがもやもやするとき、「早くスッキリしたい」と焦ってしまいますよね。
けれど、心のもやもやは「消す」ものではなく、「やわらげる」ものです。
無理にポジティブになろうとするよりも、少しずつ心を整える習慣を取り入れることで、もやもやは自然と静まっていきます。
ここでは、感受性が強く疲れやすい人でも、今日からできるもやもやする気持ちの解消法5つを紹介します。
① 感情を書き出す「ノート時間」で気持ちを整理する
もやもやしているときこそ、頭の中に浮かぶ思考を紙に書き出すことが効果的です。
心の中にあるモヤモヤは、言葉にしないままにしておくと曖昧な不安として残ります。
でも、ノートに書き出すことで「自分が何を感じているのか」が見えるようになります。
書き方のポイントは、うまく書こうとしないこと。
- いま感じている気持ちを正直に書く
- 誰にも見せない前提で、思ったまま書く
- 「どうして?」を何度か繰り返してみる
たとえば「なんか疲れた」と書いたら、「なぜ?」を重ねていく。
すると、「人に気を遣いすぎた」「言いたいことを我慢した」など、もやもやの正体が少しずつ見えてきます。
ノートは「心の鏡」です。書くことで、心の奥にある感情がやさしく整い始めます。
② 五感を整える「香り・音・光」でリセットする
感情は、思考ではなく五感から整えることができます。
たとえば、
- お気に入りの香りをそっと嗅ぐ
- 静かな音楽や自然音を流す
- 部屋の光を少し落として、あたたかな間接照明にする
こうした小さな刺激の変化は、心の緊張をゆるめてくれます。
感受性が強い人ほど、外の刺激に影響を受けやすいもの。
だからこそ、自分の感覚に「やさしい刺激」を与えてあげることが大切です。
香りや音、光を整えるだけで、心がふっと落ち着く瞬間があります。
それは、あなたの内側が「安心していいよ」と言っている証拠です。
もっと気分を休めたいときは、小さなセルフケアのリストから、今の気分に合う休み方を選んでみてください。
読むだけでも「そうか、こんな方法もあるんだ」と心がゆるむはずです。
あなたに合う“ひと休みの形”を見つけて、少しずつ自分をととのえていきましょう。
③ 「まぁいいか」と声に出して自分をゆるす
もやもやする気持ちを軽くする一番やさしい方法は、「まぁいいか」と口に出すことです。
人は、完璧を求めるほど心が張りつめてしまいます。
自分の失敗や人とのすれ違いを何度も思い出しては、「どうしてあんなこと言ったんだろう」と自分を責めてしまうこともあります。
そんなときこそ、「まぁいいか」と声に出してみてください。
声に出すことで、脳は「もう考えなくていい」と認識します。
たとえば、
- 言いたいことを我慢してしまった
- 仕事でミスをして落ち込んでいる
- 他人の反応が気になって眠れない
そんな場面で「まぁいいか」とつぶやくだけでも、心の緊張が少しほぐれます。
自分を許す言葉は、いちばん身近なセルフケアです。
④ 深呼吸+ストレッチで体から緊張をゆるめる
心がもやもやしているとき、実は体もこわばっています。
思考だけで整えようとしても、うまくいかないのは体と心がつながっているからです。
簡単な深呼吸とストレッチを数分するだけでも、頭の中のモヤが少しずつ晴れていきます。
おすすめの方法は次の通りです。
- 背筋を伸ばして、ゆっくり息を吸い込む
- 3秒ほど息を止めて、ふーっと長く吐く
- 肩や首を回して、筋肉の力を抜く
深呼吸には、体だけでなく心のリズムを整える力があります。
ストレッチを組み合わせることで、緊張がやわらぎ、「今ここ」に意識を戻すことができるのです。
もし「呼吸だけでもっとリラックスしたい」と感じたら、次の記事もあわせて読んでみてください。
深呼吸を少し意識するだけで、心の波が静まり、「落ち着く自分」を取り戻せるはずです。
⑤ 情報を減らし、静かな空間をつくる(デジタルデトックス)
もやもやの原因のひとつは、情報の多さにあります。
スマホやSNSを手放せないまま過ごすと、他人の感情や価値観がどんどん心に流れ込んできます。
デジタルデトックスとは、一時的にスマホやネットから距離をとること。
ほんの15分でも、心の呼吸が変わります。
- 夜寝る前はスマホを遠くに置く
- 朝起きてすぐニュースを見ない
- 休日はSNSを開かず、自然の音を感じてみる
そうすることで、自分の心の声が少しずつ戻ってきます。
静けさの中にいると、もやもやが小さく感じられる瞬間が訪れます。
【一緒に読みたい記事】
もやもやする気持ちは、誰にでも起こる自然な心の動きです。
無理に消そうとせず、やさしく整えることがいちばんの解消法。
感情を書き出し、香りや光を整え、「まぁいいか」と自分に声をかける。
そんな小さな習慣が、疲れた心をゆるめてくれます。
feeveraが大切にしているのは、「がんばる」よりも「ととのえる」暮らし。
あなたの心にも、静かなやすらぎが戻りますように。
もやもやが繰り返しやってくる理由|一時的に軽くしても戻ってしまうのはなぜ?

気持ちが落ち着いたと思ったのに、またすぐもやもやしてしまう。
一度スッキリしたはずなのに、数日後にはまた心が重くなる。
そんな経験はありませんか。
それは、「解消法が間違っているから」ではありません。
むしろ、正しいセルフケアをしている証拠でもあります。
ただ、心の奥にある「根っこの疲れ」が、まだ癒されきっていないだけなのです。
もやもやが繰り返しやってくるのには、いくつかの心理的な理由があります。
ここでは、その仕組みをやさしく理解しながら、“同じ気持ちに戻らないための整え方”を見つけていきましょう。
1. 感情を抑え込むクセがあると、もやもやは再発する
もやもやを何度も繰り返してしまう人の多くは、「感情を感じきる前に抑え込むクセ」があります。
たとえば、怒りや悲しみを感じても、
「こんなことで落ち込んでちゃダメだ」
「人に迷惑をかけたくない」
そうやって、感じたことをなかったことにしてしまう。
でも、感情は“消える”のではなく、“心の奥に残る”ものです。
処理されなかった思いは、時間が経ってから「もやもや」という形で再び浮かび上がってきます。
感情を我慢することは、一時的には平和を保てるかもしれません。
けれど、本当の意味で心を整えるには、「感じる勇気」が必要です。
泣くこと、怒ること、悲しむことも、すべて心の自然な動き。
押し込めるより、やさしく受け止めることが、もやもやを根本から癒す第一歩になります。
感情を抑え込むクセは、優しさの裏返しでもあります。
とくにHSPの人は、相手を思いやるあまり、自分の気持ちを後回しにしてしまうことが多いものです。
そんなときに役立つのが、「自己主張が苦手なHSPが人間関係を楽にするコツ」の記事です。
自分の気持ちをやさしく伝える方法を知ることで、心のもやもやをため込まずに、少しずつ人間関係を心地よく整えられるはずです。
2. 心が安心できる「場所」や「時間」が足りていない
どれだけ解消法を試しても、すぐにまたもやもやしてしまうときは、「安心できる時間」や「自分の居場所」が足りていないことがあります。
HSPや感受性が強い人は、外からの刺激に敏感です。
人の言葉、職場の空気、SNSの情報——それらを受け止めるたびに、心のエネルギーが少しずつ減っていきます。
心が安心できる“安全地帯”がないと、外から入ってくる刺激を整える前に、再び疲れがたまってしまうのです。
たとえば、
- 一人で静かに過ごせる「お気に入りの空間」を作る
- 誰にも気を遣わず話せる人と過ごす
- 五感がやすらぐ香りや音を日常に取り入れる
そんな「安心できる環境」を日常に増やすことが、もやもやの再発を防ぐ鍵になります。
安心できる空間は、心の回復に欠かせない大切な場所です。
もし「もっと家の中を心地よくしたい」と感じたら、暮らしをやさしく整えるヒントをまとめたこちらの記事もおすすめです。
自分らしい香りや光、素材を取り入れるだけで、家が“安心して呼吸できる場所”に変わっていきます。
あなたの心がほっとできる空間を、少しずつ育ててみてください。
3. 「頭で理解しても、心がついていかない」ズレがある
多くの人が、もやもやを解消しようとするとき、まず“考えて”なんとかしようとします。
「どうしてこんな気持ちになるんだろう」「ちゃんと考えれば、解決できるはず」——そうやって、理屈で整理しようとするのです。
でも、もやもやは“思考の問題”ではなく、“感情の反応”です。
頭では納得していても、心がまだ傷ついたままのとき、表面上の理解だけでは癒しきれません。
たとえば、
- 「もう気にしない」と言い聞かせても、胸がざわつく
- 「過ぎたこと」と思っても、思い出すたびに苦しくなる
そんなときは、「考えるより感じる時間」を大切にしてみてください。
静かな音楽を聴いたり、深呼吸をしたり、ノートに思いを書き出したり。
心が追いつく時間をあげることで、ようやく感情は落ち着いていきます。
4. 癒しが「習慣」になっていないと、心はすぐ揺れ戻る
もやもやが繰り返すもうひとつの理由は、癒しを“単発”で終わらせてしまうことです。
たとえば、落ち込んだときにだけセルフケアをして、元気になったらやめてしまう——。
そうすると、心のバランスが崩れたときに、また大きく揺れてしまいます。
心の安定は、「一度整えたら終わり」ではなく、「習慣で育てるもの」です。
1日5分でもいいから、
- 香りを感じる
- ノートに気持ちを書く
- 深呼吸する
といった“整える習慣”を続けてみてください。
小さな積み重ねが、心の防波堤になります。
繊細な人ほど、日々のやさしいルーティンが支えになるのです。
毎日の中に小さな癒しを積み重ねることが、もやもやを繰り返さないためのいちばんの近道です。
もし「何から始めたらいいかわからない」と感じたら、まずはfeeveraの無料セルフケア入門ガイドを手に取ってみてください。
きっとあなたの心にも、“これでいいんだ”と感じられる瞬間が見つかるはずです。
もやもやが繰り返すのは、あなたが弱いからではありません。
むしろ、それだけ心が繊細でまっすぐだからこそ。
感情を我慢せずに感じること。
安心できる空間を持つこと。
考えすぎず、感じる時間をつくること。
そして、整える習慣を続けること。
それらを少しずつ取り入れることで、心の波はやさしく落ち着き、もやもやは長居しなくなります。
「またもやもやしてしまった」と思ったときは、それを“失敗”ではなく“整えるチャンス”と捉えてください。
feeveraが大切にしている“休む力”は、まさにその瞬間に育っていきます。
HSP気質の人が「もやもや」から抜け出すためのセルフケア習慣
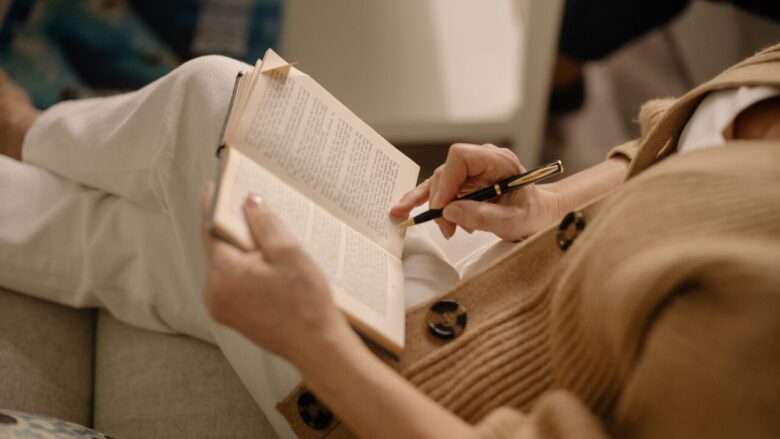
感受性が強い人は、日常のささいな刺激にも深く反応します。
人の言葉の裏を感じ取ったり、相手の気分を読み取ったり。
そんな優しさの積み重ねが、いつのまにか心を疲れさせてしまいます。
でも、HSP気質の人がもやもやしやすいのは、弱いからではありません。
それは、「感じる力」が豊かだからです。
大切なのは、その感受性を守りながら、自分を整える習慣を持つこと。
ここでは、HSP気質の人が心の静けさを取り戻すための、やさしいセルフケアを紹介します。
1. 自分を責めない思考に変える「リフレーミング」のコツ
もやもやの多くは、「自分のせいかもしれない」という自己否定から生まれます。
HSPの人は、失敗や他人の反応を深く受け止めやすいため、無意識に自分を責めてしまう傾向があります。
そんなときに役立つのが、リフレーミング(視点の切り替え)です。
物事のとらえ方を少し変えることで、心への負担が軽くなります。
たとえば、
- 「うまく話せなかった」→「緊張しても最後まで話せた」
- 「気を遣いすぎた」→「相手を思いやる力がある」
- 「弱い自分が嫌い」→「優しさを持っている自分がいる」
思考の言葉をやわらげるだけで、心のもやもやはやさしくほどけていきます。
完璧じゃなくていい。「自分を責めない練習」こそ、HSPのセルフケアの出発点です。
2. 予定を詰めすぎない“余白の時間”を意識する
もやもやが続く人の多くは、「休むこと」に罪悪感を感じています。
「もっと頑張らなきゃ」「何かしていないと落ち着かない」——そうやって自分を追い立てるうちに、心のスペースがなくなってしまうのです。
HSPの人ほど、日々の刺激に敏感です。
だからこそ、予定を詰め込みすぎず、“何もしない時間”をあえて作ることが大切です。
たとえば、
- スマホを手放して、静かな部屋でお茶を飲む
- 好きな音楽を聴きながら、ただ空を眺める
- スケジュール帳に「休息日」を書き込む
何もしない時間は、怠けではなく「心の回復の時間」。
余白があるからこそ、感情が整理され、もやもやの渦から抜け出せるようになります。
3. 「整える暮らし」で心の回復力を育てる
HSPの人は、環境の変化や雑多な空気に影響を受けやすいです。
そのため、暮らしを整えることは、心の安定にもつながります。
整えるといっても、難しいことをする必要はありません。
- お気に入りの香りを玄関に置く
- 自然素材の寝具に変えてみる
- 部屋に観葉植物を置いて、朝日を浴びる
そうした小さな工夫が、「自分を大切にしている」という安心感を育てます。
心地よい環境は、心の“居場所”になります。
毎日の中に「ほっとできる瞬間」が増えると、もやもやの波が来ても、揺れにくい心が育っていきます。
4. 他人の機嫌に振り回されない「境界線」を持つ練習
HSPの人は、人の感情を読み取りすぎてしまうため、「相手の機嫌=自分の責任」と感じてしまうことがあります。
でも、他人の感情は、あなたが背負うものではありません。
自分と相手の境界線を意識することが、心を守るカギになります。
意識のコツはシンプルです。
- 「相手の機嫌は相手の問題」と心の中でつぶやく
- 嫌なことをされたら、笑ってごまかさず「それは困ります」と伝える
- LINEの返信を後回しにしてもいいと自分に許可する
境界線を持つことは、冷たくなることではありません。
むしろ、自分の心を守ることで、本当の優しさを保てるようになります。
他人の感情に揺れないとき、あなたのもやもやは確実に減っていきます。
他人の機嫌を気にしすぎるのは、優しさがある証拠です。
でも、必要以上に相手の感情を背負い続けると、心が疲れてしまいます。
「もっと人との関わりを楽にしたい」「自分らしい距離感を学びたい」と感じた方は、次の記事もあわせて読んでみてください。
【一緒に読みたい記事】
HSP気質の人がもやもやから抜け出すには、「がんばる」より「整える」ことが何より大切です。
思考をやさしく切り替え、休む時間を作り、暮らしを整え、人との境界線を保つ——それがあなたを守るセルフケアです。
feeveraが届けたいのは、「感じすぎる自分」を否定しないでいられる居場所。優しさをそのままに、心を軽くして生きていけるように。
あなたの中のやわらかな感受性が、これからは“疲れやすさ”ではなく“生きる力”になりますように。
もやもやする日があっても大丈夫|完璧じゃなくていい心の整え方

毎日をがんばって生きていても、「今日は何をしても心が晴れない」と感じる日があります。
そんなとき、私たちはつい「どうしてこんなに弱いんだろう」と、自分を責めてしまいがちです。
でも、もやもやする日があるのは人として自然なことです。
それは心が壊れたサインではなく、「いま、休息が必要だよ」という内側の声。
完璧でいようとするほど、心はその小さな声をかき消してしまいます。
ここでは、そんな自分を責めずに、やさしく受け入れるための「心の整え方」をお伝えします。
1. もやもやは「心が感じている証拠」
もやもやするということは、心がまだ生きている証拠です。
何も感じなくなってしまうより、ずっと健康な反応です。
感受性が強い人ほど、人の気持ちや空気の変化に敏感で、日常の中で小さな違和感をたくさん拾ってしまいます。
たとえば、
- 誰かの何気ない一言がずっと心に残る
- 「ありがとう」と言われなかったことで落ち込む
- うまく笑えなかった自分にがっかりする
そんな“感じすぎる自分”を、悪いことのように思う必要はありません。
もやもやは、心がまだ“感じ取る力”を持っている証。
その感受性こそ、あなたのやさしさの源です。
2. できなかった日も、自分を責めなくていい
どんなに整える習慣を身につけても、うまくいかない日が必ずあります。
心が疲れて動けない日、気力が湧かない朝、そんなときは、「できなかった自分」ではなく「それでも今日を生きた自分」を見つめてください。
人は感情の波を完全にコントロールすることはできません。
むしろ、波があるからこそ“人らしさ”があるのです。
たとえば、
- 疲れすぎてセルフケアをサボってしまった
- 誰かに冷たくしてしまって自己嫌悪している
- SNSを見すぎて落ち込んでしまった
そんな日も、「ああ、私も人間だな」と笑ってあげてください。
休んでもいい、泣いてもいい、何もできなくてもいい。
それでもあなたは、ちゃんと前に進んでいます。
3. 少しずつ“やわらかく生きる”ことを許していこう
心のもやもやは、「こうあるべき」「ちゃんとしなきゃ」という思考から生まれます。
真面目で責任感のある人ほど、自分に厳しくしてしまう。
でも、本当の強さは“ゆるめる勇気”を持つことです。
やわらかく生きるとは、
- 自分の感情を無理に変えようとしない
- 「できること」と「できないこと」を区別して受け入れる
- 心が動いた瞬間を大切にする
たとえば、朝の光がきれいだと感じたら立ち止まる。
好きな香りに包まれて、ただ深呼吸する。
それだけでも、心は少しずつ整っていきます。
人は、完璧だから魅力的なのではありません。
ゆらぎながら、それでも自分を大切にしようとする姿にこそ、美しさがあります。
もやもやする日があっても、大丈夫です。
それは「生きている証」であり、「優しさの証」でもあります。
何もかもうまくいかない日も、心が曇る夜も、それは“自分を整える途中”で起きる自然なゆらぎです。
完璧に生きようとしなくていい。
あなたが「少しでも心地よく過ごそう」と思えた瞬間、すでに心は静かに整い始めています。
feeveraが届けたいのは、そんな“ゆらぎの中でも安心できる暮らし”です。
今日のもやもやも、やさしく包み込むように受け止めてあげてください。
体験談|もやもやする気持ちと向き合う日々
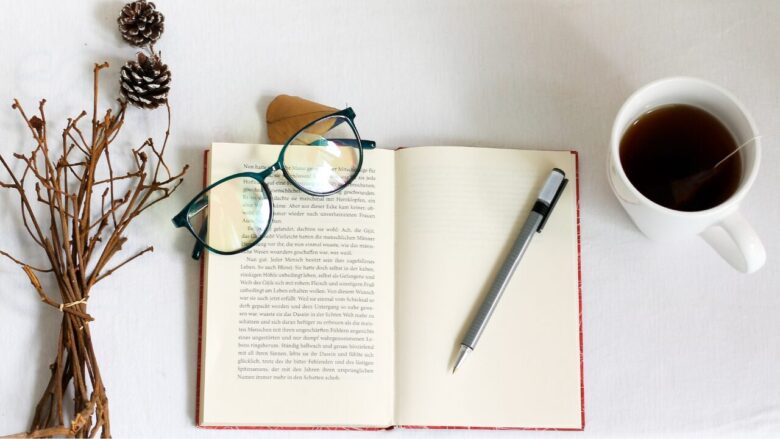
もやもやする気持ちは、どんなに整え方を学んでも、ふとした瞬間にまた顔を出します。
私も長い間、「どうにかして早く消したい」と思っていました。
でも、あるとき気づいたのです。
もやもやを“なくす”のではなく、“受け止めながら過ごす”ことで、少しずつ心がやわらいでいくということに。
誰にでも、心が曇ってどうしようもない日があります。
そんな日を、どう乗り越えてきたのか――少しだけ、私自身の体験をお話ししますね。
1. 作業や趣味に没頭して、もやもやから一歩離れる
もやもやするときこそ、何かに集中する時間を意識的に作ります。
最近は、文章を書いたり、ゲームをしたり。
一見関係のないことのようですが、“いま”に意識を向けることで、頭の中のざわめきが静まっていきます。
やりたいことに没頭していると、気づけば心の中に少しの安心が戻っている。
そんな瞬間を、何度も経験しました。
2. 外に出て、自然に気持ちを預ける
室内にこもっていると、気持ちのもやもやがまるで壁に跳ね返って戻ってくるように感じます。
だからこそ、できるだけ外に出て自然を感じる時間をつくります。
散歩に出て風を感じる。空を見上げて雲を眺める。
それだけで、心の中の重たさが少し遠くへ流れていく気がします。
自然は、何も言わずに気持ちを受け止めてくれる存在です。
とくに疲れた日は、太陽の光や風のやわらかさに救われます。
3. 「まあいいか」と思えるようになった今
どんなに深いもやもやも、時間が経てば思い出せなくなることがほとんどです。
去年のもやもやを、あなたはすぐに思い出せますか?
きっと、ほとんどの人が覚えていないはずです。
そう考えると、「いま感じている不安」も、きっと半年後にはもう遠い記憶になっています。
それを知ってから、私は「まあいいか」と少し力を抜けるようになりました。
もやもやは完全になくならなくても、“抱えたままでも大丈夫”と思えたとき、心は確かに軽くなります。
もやもやする気持ちは、悪いことではありません。
誰にでも訪れる心の波を、うまく泳いでいくように過ごせばいい。
日常の中で、自分のペースで整える。それだけで、心は少しずつやわらかくなっていきます。
まとめ
もやもやする気持ちを解消するいちばんの近道は、無理に消そうとせず、そっと受け入れることです。
もやもやは、心が「少し立ち止まって」と伝えているサイン。
感情を書き出したり、香りや光を整えたり、深呼吸をしてみるだけで、心の奥に少しずつ静けさが戻っていきます。
感受性が強い人ほど、外からの刺激をたくさん受け取り、心が疲れやすくなります。
でも、その「感じる力」は弱さではなく、やさしさの証です。
今日できる小さなセルフケアから始めてみましょう。
完璧でなくていい。
ゆっくりと自分を整える時間が、もやもやする気持ちをやわらげ、あなたの心を穏やかにしてくれます。
もやもやする日があっても大丈夫。
あなたの心には、ちゃんと回復する力が備わっています。
焦らず、やさしく、自分のペースで整えていきましょう。

私は機能不全家族のもとに育ち、人との関わりにストレスを感じやすく、常に体調不良を抱えるような「生きづらさ」を経験してきました。その経験からメンタルヘルスに強く関心を持ち、同じように苦しむ人の役に立ちたいと考えるようになりました。
最初の取り組みは「心地よさ」をテーマにした天然竹ヘアブラシの販売。そこから歩みを進め、現在は feevera(フィーヴェラ) という、生きづらさを抱える人に向けてセルフケアを届けるブランドを運営しています。
心理カウンセラー資格を活かしながら、
五感にやさしいセルフケア
心がふっと軽くなる生き方のヒント
繊細さを否定しない暮らしの提案
を発信し、少しでも「安心できる時間」を届けられるよう活動しています。