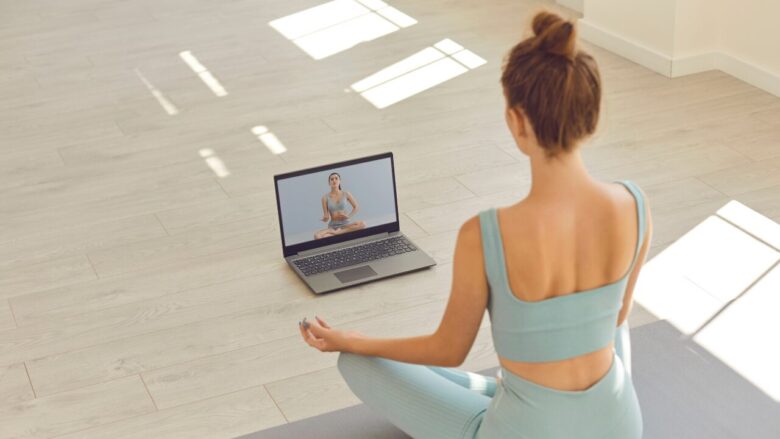最終更新日:2025.09.24
また夜が更けていくのを、息を潜めるように過ごした人もいるかもしれません。
「どうしていつも人間関係がうまくいかないのか」
「気づけば、また自分を責めてしまっている」
そう感じながら、心の中に重たい疲れを抱えている人は少なくありません。
インナーチャイルドとは、幼い頃に心の奥にしまい込んだ感情や傷ついた記憶のこと。
その存在が、大人になった今も知らず知らずのうちに、生きづらさの原因になっていることがあります。
子ども時代の寂しさや恐怖が、今の人間関係や自己肯定感に影を落とす──
そんな実感を抱えながらも、「自分を変えたい」「もっと楽に生きたい」と願っている方もいるでしょう。
本記事では、インナーチャイルドの意味や特徴、そして癒し方までをわかりやすく解説します。
生きづらさの根っこにやさしく光を当てる時間として、どうぞご覧ください。
インナーチャイルドとは幼少期の傷と影響

心が敏感すぎて疲れやすいときや、人間関係で同じ苦しみを繰り返すとき、ふと「自分はなぜ生きづらいのだろう」と考えることがあります。
その答えを探す鍵のひとつが、「インナーチャイルドとは何か」という問いです。
とくにHSP気質の人は、幼い頃の心の傷が大人になっても影響しやすく、過去の自分を癒すことが今の自分を救う道になることがあります。
ここでは、「インナーチャイルドとは」という基本から、幼少期の傷とのつながり、さらにアダルトチルドレンとの関係まで、わかりやすくお伝えします。
インナーチャイルドとは何か?心理学的な定義と意味
インナーチャイルドとは、心の中に生き続ける「子どもの頃の自分」のことです。
幼い自分の感情や記憶、経験が大人になっても無意識のうちに心に残り、考え方や行動に影響を与えます。
その理由は、幼少期の体験が「自分はこういう人間だ」という深い思い込みをつくり、人生の土台になってしまうからです。
例えば、いつも親に怒られていた人は「自分は愛されない存在だ」と感じ、大人になっても人の顔色をうかがってしまうことがあります。
「わかる、そんなふうに無意識に心が縛られるのがつらいよね」と感じる人も多いでしょう。
インナーチャイルドが幼少期の傷になる理由
インナーチャイルドは本来、純粋さや好奇心を持った存在ですが、幼少期に傷つく体験をすると心に痛みを抱えたまま成長します。
幼い心はまだ物事を正しく理解できず、「自分が悪いから怒られた」とか「自分は価値がない」と思い込んでしまうためです。
こうした思い込みが大人になっても消えず、同じような苦しみを繰り返す原因になるのです。
例えば、親から厳しく叱られて育った人が、大人になっても他人の期待に応えようと無理をしてしまうことがあります。
「わたしもそう。自分が責められている気がして苦しくなる」と共感する方もいるかもしれません。
アダルトチルドレンとインナーチャイルドの関係
アダルトチルドレンとは、機能不全の家庭で育った人が、大人になっても生きづらさを抱え続ける状態をいいます。
その背景には、癒されていないインナーチャイルドが潜んでいます。
なぜなら、子ども時代の心の傷や恐怖が大人の人間関係や自己イメージに強く影響するからです。
例えば、お酒に頼る親のもとで育った人が「人は信じられない」と感じ、大人になっても親密な関係を築けないことがあります。
「私も家ではいつも緊張していた」「安心できる場所がなかった」という人にとって、このテーマは自分の物語のように感じるかもしれません。
アダルトチルドレンに関しての詳しい内容は以下の記事で解説しています。
インナーチャイルドとはなぜ生きづらさの原因になるのか

「どうしてこんなに疲れやすいのか」
「人といると息が詰まるのはなぜか」
そう感じてしまう人にとって、インナーチャイルドとは、ただの昔の思い出ではなく、今の生き方に深く関わる存在です。
ここでは、インナーチャイルドが生きづらさを生む理由を、HSPの特性や家庭環境との関わり、人間関係での苦しみのパターンから解き明かします。
HSPが感じる生きづらさとインナーチャイルド
インナーチャイルドとは、HSPが抱える繊細さと密接に関わっています。
HSPは感覚も感情も敏感なため、過去のつらい体験を強く記憶に刻み込みやすいのです。
そのため、小さなきっかけで心が傷つき、子どもの頃の恐怖や悲しみがよみがえり、日常が生きづらくなります。
例えば、上司に少し声を荒げられただけで「また自分はダメなんだ」と落ち込んでしまうことがあります。
「わかる、たった一言で心がズタズタになることってあるよね」と思う人も多いでしょう。
親子関係や家庭環境が与える影響とは
インナーチャイルドとは、親子関係や家庭環境の影響を強く受けています。
子どもは親の言葉や態度を絶対だと思い込み、「愛されるためにはいい子でいなければ」と自分を抑え込むことが多いのです。
その結果、大人になっても「嫌われたくない」という思いから、自分を犠牲にしてしまう人が少なくありません。
例えば、親が厳しかった人ほど、職場でも他人の期待に応えようと限界まで頑張ってしまうことがあります。
「私も、気づくといつも自分を押し殺している」と感じる方もいるかもしれません。
人間関係のパターンとインナーチャイルドの関連性
インナーチャイルドとは、繰り返す人間関係のパターンとも深く関係しています。
なぜなら、子どもの頃に刷り込まれた「自分は愛されない」「怒られる存在」という思い込みが、大人の人間関係の選び方に影響するからです。
そのため、無意識に支配的な相手を選んだり、相手に尽くし過ぎて疲れ果てたりすることが多いのです。
例えば、恋愛で相手にすべてを合わせてしまい、自分のことが分からなくなる人もいます。
「それ、まさに私のことかもしれない」とドキッとする人もいるでしょう。
インナーチャイルドとはどう向き合うべきか

過去の傷を抱えたまま生きるのは、とても苦しいことです。
しかし、インナーチャイルドとは、向き合うことで少しずつ癒すことができます。
ここでは、セルフケアの方法や、カウンセリングでの扱い、HSPの人が日常でできる小さな工夫まで、やさしくお伝えします。
「変わりたい」と願うあなたの力になれるように。
インナーチャイルドを癒すセルフケアの方法
インナーチャイルドを癒す第一歩は、自分の心に耳を傾けることです。
理由は、過去の痛みを無視すると、さらに苦しみが大きくなるからです。
以下のようなセルフケアが、少しずつ心をほぐす助けになります。
- 日記を書くことで自分の本音を知る
- 「大丈夫だよ」と自分に優しい言葉をかける
- 安心できる空間で深呼吸する
例えば、夜寝る前に「今日はよく頑張ったね」と自分に声をかけるだけでも、心が少し軽くなることがあります。
「それならできそう」と感じる人もいるのではないでしょうか。
セルフケアについては以下の記事が参考になります。
カウンセリングでのインナーチャイルドの扱いとは
インナーチャイルドとは、カウンセリングの場でも大切に扱われるテーマです。
専門家と一緒に過去の感情を整理することで、自分を責める苦しさが和らぐことがあります。
理由は、安心できる場所で話すことで「本当はどう感じていたか」に気づけるからです。
例えば、「親が怖かった」と打ち明けた瞬間、涙が止まらなくなる人も少なくありません。
「自分だけじゃない」と知ることで、ほっとする方も多いでしょう。
HSPに寄り添うカウンセリングの特徴は以下の記事で解説しています。
HSPが日常でできるインナーチャイルドケア
HSPは感受性が強いため、日常の小さな刺激でも心が疲れやすいです。
そのため、インナーチャイルドとは、日々の小さなケアの積み重ねが大切です。
以下のような方法を試すと良いでしょう。
- 自然に触れて心を落ち着ける
- 無理に人と比べず、自分のペースを守る
- 心が乱れたらその場から離れる勇気を持つ
例えば、空を見上げるだけでも「自分はここにいていい」と感じられる瞬間があります。
「そういう小さなことで救われるんだよね」と感じる方も多いのではないでしょうか。
まとめ
インナーチャイルドとは、幼少期に刻まれた記憶や思い込みが、今の生きづらさに影響している心の存在です。
自分は価値がない、誰にも本音を見せてはいけない──
そんな深い思い込みが、今もあなたの心を苦しめているかもしれません。
でも、それはあなたが弱いからではなく、「守るため」に覚えた心のクセ。
そのことに気づき、少しずつ優しくほどいていくことが、回復の第一歩になります。
小さなセルフケアを重ねたり、信頼できる人に話してみたり。
できるところからで構いません。
あなたの中の「小さな自分」を否定せず、労わること。
それが、これからの生き方を変えていく力になります。
生きづらさの奥にある、あなたの本当の声に耳を澄ませていきましょう。

私は機能不全家族のもとに育ち、人との関わりにストレスを感じやすく、常に体調不良を抱えるような「生きづらさ」を経験してきました。その経験からメンタルヘルスに強く関心を持ち、同じように苦しむ人の役に立ちたいと考えるようになりました。
最初の取り組みは「心地よさ」をテーマにした天然竹ヘアブラシの販売。そこから歩みを進め、現在は feevera(フィーヴェラ) という、生きづらさを抱える人に向けてセルフケアを届けるブランドを運営しています。
心理カウンセラー資格を活かしながら、
五感にやさしいセルフケア
心がふっと軽くなる生き方のヒント
繊細さを否定しない暮らしの提案
を発信し、少しでも「安心できる時間」を届けられるよう活動しています。