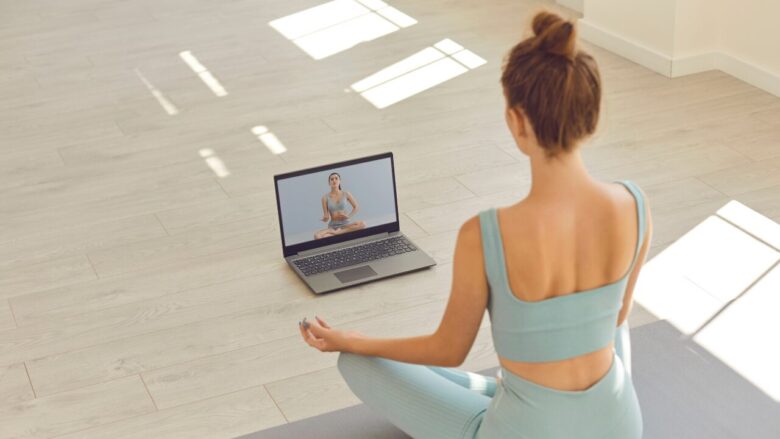最終更新日:2025.11.18
「また、自分を責めてしまった……」
そんな小さな声が、心の奥でくり返し響いていませんか?
何度も繰り返す後悔や不安。
まわりの期待に応えようとして、気づけば自分の気持ちは置き去り。
「どうしてこんなに疲れるんだろう」
「もっとラクに生きられたらいいのに」
そんな思いを抱えながらも、前に進みたい。
その気持ちがあるなら、あなたはもう一歩を踏み出す準備ができています。
ここからは、心が疲れやすいあなたでも無理なく続けられる、自己肯定感を高める7つのセルフケア習慣をご紹介します。
「それでも大丈夫」と自分を認められる未来を、一緒に見つけていきましょう。
わたし自身も、自己肯定感の低さに長く悩んできた

わたしも、自己肯定感がないと感じてきた時間がとても長くありました。
自分をそのまま受け入れることが難しく、心のどこかでいつも「どうして自分だけこんな目に合うんだろう」と過去の育った環境と現実のギャップに苦しんでいました。
みんなは好きな道を選び、自由に進んでいるのに、わたしは我慢し、言われるままに進んで、うまくいかなかったときはすべての責任が自分に転がってくる。
そんな出来事をくり返すたびに、「やっぱり自分はだめなんだ」と思い込み、どんどん自信を失っていきました。
生きづらさを抱えたまま、悩んで、悩んで、それでもなんとか前に進んできたけれど、「ありのままの自分でいい」と思うことは簡単ではありませんでした。
それでも、ある時から少しずつ、完璧ではない自分にも「それでいいよ」と言い聞かせてみたら、心の中で固まっていたものが、ゆっくりほどけていく感覚がありました。
すぐには変われなくても、自分を否定しない時間を増やしていくことで、以前よりも心が軽くなってきたと思えるようになったのです。
だからこそ今、「自己肯定感を高める」というテーマにわたし自身が深く向き合ってきた体験を添えて、この記事を届けたいと思っています。
自己肯定感の高め方を始める前に|基礎理解

気持ちが沈む日、「自分なんて」と思ってしまう瞬間はありませんか。
自己肯定感は、そうした思い込みから自分をやさしく引き離し、本来の心の穏やかさを取り戻すための土台になります。
まずは「自己肯定感ってなんだろう」という疑問から、一緒にほどいていきましょう。
自己肯定感とは?自尊感情との違いを整理
自己肯定感とは、うまくいかない日でも「それでも私は大丈夫」と思える気持ちのことです。
よく似た言葉に「自尊感情(自尊心)」がありますが、これは「自分には価値がある」と感じる評価に近い感覚です。
自己肯定感は「存在そのもの」への信頼、自尊感情は「行動や成果」に対する評価と言えるでしょう。
たとえば、失敗して落ち込んだときでも「私はダメな人間」とは思わず、「うまくいかなかったけど、私は私」と思える状態が、自己肯定感が保たれている状態です。
自己肯定感が下がりやすい3つの背景
繊細で感受性が強い人は、自己肯定感が揺らぎやすい特徴があります。
まず、人の表情や言葉の裏に敏感に反応しやすいため、「もしかして怒っていたのかな」と必要以上に自分を責めてしまうことがあります。
次に、真面目で責任感が強いため、「もっと頑張らなければ」と自分を追い込みやすい傾向も。
休むことが苦手で、心と体のバランスを崩しがちです。
そして、人の気持ちに共感しすぎるあまり、つい自分より他人を優先してしまい、「自分には価値がないのかもしれない」と感じてしまうこともあります。
「誰かの役に立てない自分に意味があるのだろうか」と思う瞬間は、自己肯定感が大きく揺らぐサインかもしれません。
自己肯定感を高めるメリットと注意点
自己肯定感が高まると、他人の評価に過剰に振り回されることが減り、自分の軸で選択できるようになります。
感情の波に飲み込まれにくくなり、「こう感じてもいい」「これが今の自分」と、気持ちを受け止める力が育っていきます。
ただし、無理に高めようとしすぎると、かえって「ポジティブでいなければ」と自分を追い詰めることもあるため注意が必要です。
まずは、ありのままの自分に「それでも大丈夫」と言ってあげられる瞬間を、少しずつ増やしていくことから始めましょう。
自己肯定感を高めるときのポイント

自己肯定感を育てたいと思っても、繊細な心を持つ人は無意識のうちに自分を責めたり、疲れてしまうことがあります。
だからこそ、ただ方法を試すだけでなく、自分の特性やペースに合ったやり方を選ぶことがとても大切です。
ここでは、安心して自己肯定感と向き合うためのヒントをお伝えします。
刺激に敏感な脳を守るセルフモニタリング法
繊細な心は日々の刺激を強く受け取りやすく、頭がずっとフル回転状態になってしまいがちです。
そんな状態で自分の感情や考えを無視すると、知らず知らず「自己否定」のクセが強まることもあります。
まずは、自分の心と体の反応に気づくことから始めましょう。
- 今、何に緊張しているのか
- どんな言葉に反応して疲れたのか
- 本当は、何を感じていたのか
こうした内面の変化を、紙に書き出すだけでも、自己否定の流れをやさしく断ち切ることができます。
自分を観察することは、自分を守る第一歩です。
「がんばり過ぎ」を手放す3つの視点
自己肯定感が低くなっているとき、つい「もっと頑張らなきゃ」「自分はまだまだ」と自分を追い込みがちです。
でも、実はがんばり過ぎている自分に気づいていないことも多いもの。
次の3つを意識してみてください。
- 「休むこと」は甘えではなく、回復のプロセスである
- 他人の期待より「今の自分にできること」を選ぶ
- 「できなかったこと」より「できたこと」に注目する
無理してがんばらなくても、あなたの存在に価値があることは変わりません。
人に依存しない生き方のススメ!解放されるための具体的な方法 もぜひ読んでみてください。
自己肯定感を下げるNG習慣と手放し方
知らず知らずのうちに、自己肯定感を下げてしまう習慣が身についていることがあります。
たとえば、
- 「ごめんなさい」が口癖になっている
- SNSで他人と自分を比べてしまう
- ちょっとした失敗を何日も引きずってしまう
こうした習慣は、HSPの人にとって特に心の負担となりやすいものです。
まずは、「自分を否定しない言葉」を意識して使ってみてください。
「ありがとう」
「よくやってるね」
「うまくいかなくても大丈夫」
そうした言葉が、自己肯定感を育てるやわらかな土壌になります。
今日から実践!自己肯定感を高める7つの習慣

知識だけでは、心はなかなか変わってくれません。
大切なのは、「行動」を通して、少しずつ自己肯定感を積み上げていくこと。
完璧を目指す必要はありません。
ひとつでも、「これはできそう」と思える習慣から取り入れてみてください。
朝|「できた」を書き出すモーニングジャーナル
朝、ほんの数分でも「できたこと」をノートに書き出すと、1日のはじまりが少し明るくなります。
- 起きられた
- 顔を洗った
- 今日を生きる準備ができた
小さな行動を言葉にすることで、「ちゃんと動けている自分」を実感できます。
「今日もダメかも」と思いやすい朝こそ、自分へのやさしい声かけを習慣にしてみましょう。
日中|自然音+深呼吸で感覚を整えるルーティン
仕事や家事、外の刺激に疲れたときは、静かな自然音を流しながら深呼吸をしてみてください。
鳥のさえずりや雨音、風の音など、HSPの人にとって心を静める手助けになります。
深く吸って、ゆっくり吐くだけで、頭の中のざわつきがすこしずつほどけていきます。
「整える時間」を持つだけで、「何もできていない」という焦りがやわらいでいきます。
夜|「それでいいよ」とセルフタッチで締めくくる
1日が終わるころ、「もっとやれたはず」と自分を責める気持ちが出てくることはありませんか。
そんなときは、胸に手を当てて「今日もよくやったね」「それでいいよ」と静かに伝えてみてください。
手の温かさには、脳と心を落ち着かせる力があります。
眠る前のセルフタッチは、「自分と和解して終える」やさしい習慣になります。
週末|デジタルデトックス&五感リセット散歩
週末のスマホやSNSから少しだけ離れて、自然のある場所を歩いてみましょう。
風のにおい、光の加減、葉っぱの音……五感を使うことで、今この瞬間に意識が戻ってきます。
情報に疲れた心を、自然のリズムでリセットすることは、自己肯定感の回復にもつながります。
歩くペースは遅くていい。立ち止まって空を見上げる時間を、どうか大切にしてください。
対人|境界線を守るIメッセージ練習
HSPの人は、つい相手を優先してしまい、自分の気持ちを後回しにしてしまいがちです。
しかし、本当に自分を大切にするには、「嫌だ」と伝える勇気も必要です。
そんなときに役立つのが「I(アイ)メッセージ」。
「あなたが悪い」ではなく、「私はこう感じている」と伝えることで、相手との関係性を壊さず、自分の境界線を守ることができます。
たとえば、「私は一人の時間も大切にしたいと感じています」と伝えるだけでも、罪悪感が少なくなります。
仕事|タスク分解で小さな達成感を積み上げる
「完璧にやらなきゃ」と感じると、何も手をつけられなくなることがあります。
そういうときは、大きな仕事を小さなステップに分けて、一つひとつ達成していくことが効果的です。
- パソコンを開く
- 資料を1ページ読む
- 3分だけ集中する
どんなに小さくても「できたこと」は、自己肯定感を支える貴重な材料です。
思考|ネガティブを書き換えるリフレーミング
つい「自分はだめだ」「なんでこんなこともできないの」と思ってしまうときは、言葉の角度を変えてみましょう。
「だめ」ではなく「まだ慣れていない」
「できない」ではなく「今は準備中」
言葉を変えるだけで、見える世界が変わっていきます。
心の中にいる「やさしいもうひとりの自分」が、そうやって声をかけてくれるようになります。
ネガティブコミュニケーションの記事も参考になります。
失敗しても「大丈夫」と思えるようになった理由
以前の私は、小さなミスひとつで何日も落ち込み、気持ちが沈んだままさらにミスを重ねてしまう…そんな悪循環を繰り返していました。
「なんで自分はこんなにダメなんだろう」と自分を責め続ける日々。仕事に行くのが苦痛になることもありました。
でもあるときから、失敗したら「なんとかなる」と自分に言い聞かせる習慣を持つようにしました。
最初は心の中でつぶやくだけ。それでも不思議と、必要以上に引きずらずに済むようになったんです。
そして気にせず仕事に打ち込んでいると、数日後には「そういえばあのときのミス、もう忘れていた」ということが増えてきました。
大きな失敗も、ちいかわのハチワレのように“なんとかなる精神”で受け入れる。
「失敗しても大丈夫。私はここからやり直せる」
そう思えるようになったら、以前のように長く落ち込むことは少なくなり、自然と自己肯定感が少しずつ育っていきました。
習慣を続け自己肯定感を高めるコツと支援ツール

どんなに良い習慣も、続けられなければ意味がない。
そう思って、途中であきらめてしまった経験はありませんか。
でも本当は、続けるために必要なのは「意志の強さ」ではなく「仕組み」です。
ここでは、自己肯定感を高める習慣を無理なく続けるためのコツと、役立つツールをご紹介します。
継続を助ける「トリガー+報酬」メソッド
習慣化の基本は、「行動のきっかけ」と「小さなごほうび」をセットにすることです。
たとえば、
- 朝の歯みがき後に1分だけノートを開く
- 散歩のあとに自分に温かいお茶を淹れてあげる
こうした“トリガー”と“報酬”を組み合わせると、自然に行動が身についていきます。
毎日でなくてもかまいません。
「できた日があった」ことを自分で認めることが、何よりも大切な成果になります。
自己肯定感チェックリスト&記録アプリ活用
言葉にして記録することは、自己肯定感を育てるうえで大きな力になります。
気持ちの波を見える化することで、自分の変化に気づきやすくなり、「前よりラクに感じている」と実感できるようになります。
おすすめの方法
- 日々の気分を数値でつけて、週ごとにふりかえる
- 「できたことリスト」や「感謝したこと」を毎日ひとつ書く
- アプリで習慣の記録やリマインダーを設定する
スマートフォンの中に「やさしい自分を応援する空間」をつくるような気持ちで、無理なく続けてみてください。
セルフケアPDFやコミュニティの活用法
ひとりでセルフケアを続けるのが難しいと感じるときは、同じような感覚を持つ人たちとつながることが大きな支えになります。
feeveraでは、繊細な心に寄り添うセルフケアPDFを販売しています。
静かな時間にじっくり向き合い、自分の心と対話するサポートとして活用できます。
また、気持ちをわかってくれる仲間がいるコミュニティやグループに参加すると、安心感が生まれます。
誰かと比べるのではなく、自分を大切にすることを思い出せる場所として、ぜひ自分に合ったツールを選んでみてください。
まとめ
自己肯定感を高めることは、「今の自分を否定すること」ではありません。
「できない日があった」ときこそ、「それでも自分を受け入れる」力が、内側に安心感を育ててくれます。
今回ご紹介した7つの習慣は、どれも完璧であることより、“やさしく続けること”を大切にした方法です。
- 朝の「できたこと」日記
- 静かな自然音と深呼吸
- 「それでいいよ」と自分にかけるひとこと
どれか一つでも「これならできそう」と感じたら、今日からやってみてください。
あなたの心の土台は、小さな肯定の積み重ねで、静かに強くなっていきます。
feeveraはこれからも、「生きづらさを抱える心」にそっと寄り添いながら、“休む力”を育てるセルフケアのヒントをお届けしていきます。

家庭や人間関係の中で安心できず、生きづらさを抱えてきました。その経験から、心を守り整えることに目を向け、現在は feevera(フィーヴェラ)として、繊細さを否定しないセルフケアや、心が落ち着く生き方のヒントを届けています。