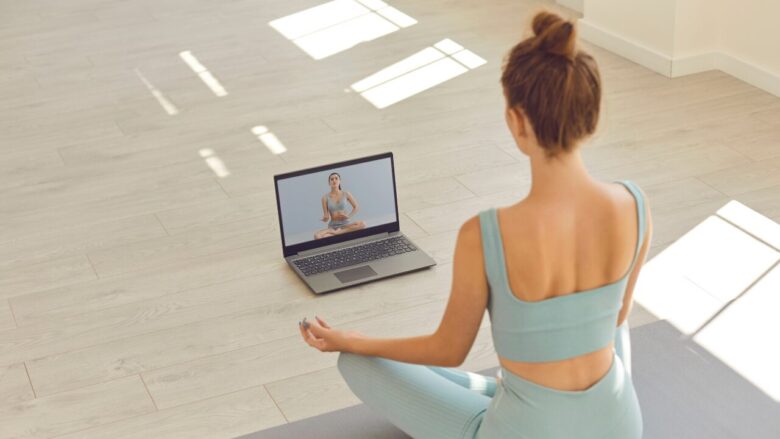最終更新日:2025.11.18
「どうしてこんなに生きづらいのだろう」
ふとした瞬間にそう感じて、胸が苦しくなることはありませんか。
人間関係で気を遣いすぎたり、仕事で小さな失敗を引きずったり、休みたいのに休めなかったり。
自分を責める思考から抜け出せず、「弱い自分が悪い」と感じてしまう人は少なくありません。
しかし、生きづらさには必ず原因があります。
気質の影響や過去の経験、職場や社会のプレッシャーなどが重なって、心を疲れやすくしているのです。
決して「あなたの努力不足」や「性格の欠点」ではありません。
原因を知ることは、自分を理解し直し、心をととのえる大切な第一歩になります。
この記事では「生きづらさの原因」について詳しく解説し、理解を深めながら安心につながるヒントをご紹介します。
「自分だけが苦しいわけではない」と思えるきっかけを探している方は、ぜひ最後まで読み進めてください。
生きづらさと共に歩いてきた私の日常

私は、ずっと「生きづらさ」と一緒に生きてきました。
朝起きた瞬間から理由もなく体が重く、息をするだけで疲れてしまう日もあります。
仕事の前には緊張が高まり、胸の奥がそわそわして、まるで自分の体が自分のものじゃないように感じることさえあります。
突然強烈な眠気にのみ込まれたり、人と話すだけで顔がこわばり、頬が熱くなる。
「普通に話すだけなのに」と頭でわかっていても、体は思うように動いてくれません。
過去の記憶が突然よみがえることもある
一人になったとき、ふと幼い頃の家庭のことを思い出すことがあります。
くずみたいだった親の言動。
理不尽な怒り、突然の沈黙、気を遣い続けていたあの日々。
「なんで私ばかり我慢しなきゃいけなかったんだろう」
「どうしてあんな扱いを受けなきゃいけなかったんだろう」
心の奥でくすぶっていた怒りが、今でもふっと顔を出すことがあります。
それだけ、あの頃の影響が今も体に残っているのだと感じます。
生きづらい日々の中にも、小さな前進がある
大人になってからも、生きづらさは急に波のように押し寄せて、仕事で少しつまずいただけで心が折れそうになったり、人間関係のちょっとした一言に深く傷ついてしまう自分が嫌になることもありました。
だけど、こうした反応は「弱さ」ではありません。
ずっと張りつめて生きてきた体と心が、やっと「助けて」と言えるようになった証だと、少しずつ理解できるようになりました。
私が続けている「無理のないセルフケア」
生きづらさは消えるものではありません。
でも、小さな習慣が、確実に私を救ってきました。
深呼吸をして胸の緊張をゆるめること。
疲れが抜けない日は早く横になること。
自然の音や静かな時間に身を委ねること。
気持ちが揺れた日はノートに書き出すこと。
どれも特別なことではありませんが、心の波がゆっくりと落ち着いていくのを感じます。
「今日をどう穏やかに過ごすか」を考えるのが、いつの間にか毎日の小さな日課になりました。
生きづらさは消えなくても、楽に生きられる日は増えていく
生きづらさは私のライフそのものです。
付き合い方に悩んだり、疲れ果てたり、涙が出る日もあります。
それでも、小さな工夫やセルフケアを積み重ねることで、
「今日は少し楽だったな」
「昨日より息がしやすいな」
そんな瞬間が確かに増えてきました。
同じような苦しさを抱えている人にも、そんな一歩が必ずあると信じています。
あなたが少しでも自分を責めずに、静かに息ができる時間が増えますように。
生きづらさの原因を知ることが心を軽くする第一歩
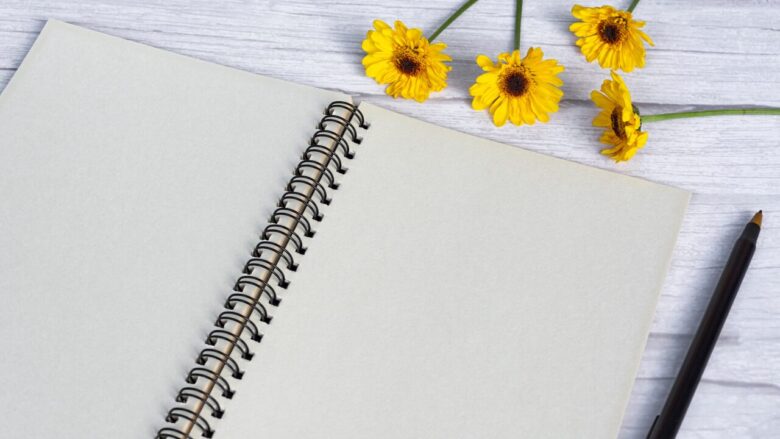
人は理由がわからないままつらさを抱えると、必要以上に自分を責めてしまいます。
しかし「生きづらさには原因がある」と知ることは、心を軽くする最初の一歩になります。
1. なぜ多くの人が「生きづらさ」を感じるのか
多くの人が生きづらさを抱えるのは、単に性格が弱いからではありません。
生きづらさは、気質や過去の経験、そして社会のあり方が重なり合って生まれるものです。
たとえばHSPの人は、周囲の小さな変化や他人の気持ちを敏感に感じ取りやすいため、日常の刺激が強すぎて疲れやすくなります。
また、家庭や職場で安心を得られなかった経験があると、「どこでも居場所がない」と感じやすくなります。
「どうして自分だけ…」と思っても、それは多くの人が共通して感じているものです。
2. 生きづらさを「自分のせい」と思い込みやすい理由
生きづらさを抱えた人の多くは、真面目で責任感が強い人です。
そのため、環境や人間関係によって苦しんでいるのに「弱い自分が悪い」と考えてしまいがちです。
たとえば、仕事で疲れ果てていても「周りはできているから、自分が足りないのだ」と思い込む。
家庭で安心できなくても「耐えられない自分に問題がある」と考える。
こうした思い込みは、さらに自己否定を深め、生きづらさを増してしまいます。
本当は環境や背景に原因があることを知ることが大切です。
3. 原因を整理すると気持ちが楽になる理由
原因を整理することで、「自分の弱さ」ではなく「状況や気質の影響」だと理解できるようになります。
そうすると、必要以上に自分を責めずにすみ、心に少しずつ余裕が生まれます。
たとえば
- HSP気質が影響している
- 家庭や過去の人間関係に由来する
- 職場や社会のプレッシャーが強すぎる
と分けて考えるだけでも「だからしんどかったんだ」と納得でき、安心感につながります。
気づきはすぐに生きづらさをなくすわけではありません。
しかし、自分を理解することは、心をととのえるための大切なスタートラインになります。
生きづらさの原因|気質・環境・社会的要因
生きづらさには必ず背景があります。
それは一つの要素だけではなく、気質や過去の体験、そして社会のあり方が重なり合って生まれるものです。
「自分が弱いから苦しいのだ」と考えてしまいがちですが、実際には外側の環境と内側の気質が影響し合っているのです。
ここでは、生きづらさを感じやすくする代表的な原因を整理してみましょう。
1. HSPや感受性の強さが影響する生きづらさ
生まれつき感受性が強い人、いわゆるHSP(Highly Sensitive Person)は、五感や心のセンサーが人一倍鋭く働きます。
小さな音や光、人のちょっとした表情の変化まで敏感に察知し、それを強い刺激として受け取ります。
この敏感さは「人に深く寄り添える力」でもありますが、刺激が多すぎる社会の中では心身に大きな負担となりやすいのです。
たとえば、オフィスの雑音や会話の温度感に疲れてしまい、「なぜ自分だけ疲れてしまうのだろう」と悩む人も少なくありません。
これは弱さではなく、感じ取る力が豊かだからこそ起きることです。
2. 家庭環境や過去の人間関係がもたらす影響
幼い頃や過去の人間関係で安心を得られなかった経験は、大人になってからも生きづらさの土台となることがあります。
否定的な言葉を浴び続けたり、気持ちを受け止めてもらえなかった経験があると、自分を信じる力が弱まりやすいのです。
その結果、「どうせ理解されない」「また否定される」という思い込みが強くなり、人との関係に緊張や不安を抱えてしまいます。
本来なら安心を育むはずの人間関係が、逆に「恐れ」の感覚を残してしまう。
そうした過去の積み重ねが、現在の生きづらさに深く影響しているのです。
もし家庭環境や親子関係の影響で苦しさを抱えているなら、アダルトチルドレン(AC)の視点から理解することも役立ちます。
詳しくは「ACを自分で治す方法|過去に縛られぬ生き方へ」で、具体的な向き合い方を紹介しています。
3. 職場・社会のプレッシャーが心を追い込む要因
社会や職場で求められる「効率」「強さ」「成果」は、感受性が強い人にとって大きなプレッシャーとなります。
スピード重視の働き方や人間関係のストレス、過度なノルマは、繊細な心を疲れさせる大きな要因です。
周りが普通にこなしているように見える状況で、自分だけが苦しいと感じると「やっぱり自分はダメなんだ」と自己否定に陥りやすくなります。
しかし、これは個人の能力の問題ではなく、社会の仕組みと個人の気質との相性の問題です。
「努力不足」ではなく「環境との不一致」が原因であることを知るだけでも、心は少し楽になります。
4. 完璧主義や自己否定のクセが生きづらさを深める
「失敗してはいけない」「人に迷惑をかけてはいけない」という思いが強すぎると、常に緊張の中で生きることになります。
ほんの小さなミスでさえ「自分は価値がない」と感じ、心を大きく消耗してしまうのです。
完璧主義は努力の証のように見えますが、心には過度なプレッシャーを与えます。
さらに自己否定のクセと重なると、生きづらさはどんどん深まり、抜け出せない悪循環をつくり出します。
たとえば、職場で一度叱られただけで「自分はもう役に立てない」と考えてしまうことがあります。
しかし、これは性格の弱さではなく「真面目すぎる思考のクセ」が背景にあるのです。
5. 自己表現のしづらさが生きづらさにつながる
自分の気持ちを素直に表現できないことは、生きづらさを強める大きな要因です。
特に繊細で人に気を遣いやすい人は、「嫌われたくない」「迷惑をかけたくない」と思い、自分の本音を抑えてしまいます。
その結果、心の中に「言いたいけれど言えない気持ち」が積み重なり、自分を否定する感覚につながります。
たとえば、職場で納得できないことがあっても我慢し続けたり、家族の前で本音を隠して過ごしたりすることです。
「ありのままの自分を出せない」ことは、孤独感や無力感を育て、生きづらさを深めてしまいます。
もし「自己表現が苦手で人間関係に疲れてしまう」と感じるなら、少しずつ心を楽にする工夫があります。
詳しくは関連記事「自己主張が苦手なHSPが人間関係を楽にするコツとは」で紹介していますので、あわせて読んでみてください。
6. 比較やSNSによる情報過多が心を追い込む
現代社会では、SNSやネットを通じて常に他人の暮らしや成功が目に入ります。
その情報量の多さは、自分の生活と比較してしまう大きなきっかけになります。
「みんなはうまくやっているのに、自分だけが取り残されている」
「友人は楽しそうにしているのに、自分は何もできていない」
そんなふうに感じることで、自己否定や焦りが強くなり、生きづらさを深めてしまいます。
本来は必要ない比較でも、SNSを通して日常的に繰り返されることで、心にプレッシャーがかかるのです。
【一緒に読みたい記事】
7. 経済的不安や将来への心配が安心感を奪う
生きづらさの背景には、経済的な不安や将来への漠然とした心配も大きく関わっています。
お金や仕事の安定は「安心して生きるための土台」であり、それが揺らぐと心は常に緊張した状態になります。
たとえば、収入が不安定で「来月の生活費は大丈夫だろうか」と不安に思うことや、将来の老後や健康に関して強い心配を抱えることです。
心の安心は生活の安定とつながっています。
「明日をどう生きるか」に追われる状況は、生きづらさを大きく膨らませてしまうのです。
8. トラウマや過去の傷が生きづらさを残す
過去のつらい経験や心の傷は、大人になってからも影響を与え続けます。
いじめ、虐待、裏切りなどの体験は、無意識のうちに「また同じことが起きるかもしれない」という恐れを生みます。
そのため、安心して人間関係を築けず、常に警戒心を抱いてしまいます。
「信じたいのに信じられない」という矛盾が心を疲れさせ、生きづらさを強めるのです。
たとえば、過去に否定され続けた人は、新しい出会いでも「どうせ理解してもらえない」と身を引いてしまうことがあります。
心の傷を少しずつ癒す習慣を持つことは、生きづらさを和らげるうえで大切な視点です。
詳しくは「心の傷を癒す習慣|トラウマ・ストレスを和らげる方法」で具体的な向き合い方を紹介しています。
9. 社会的な孤独やつながりの希薄さが心を弱らせる
人は誰しも安心できる居場所や人とのつながりを必要としています。
しかし、現代は人との関係が希薄になりやすく、孤独を感じる人が増えています。
「悩みを打ち明けられる相手がいない」
「本音を話せる場所がない」
そんな状況は、孤独感を深め、生きづらさを増幅させます。
特に、同じ気持ちを共有できる相手がいないと「自分だけが取り残されている」と感じやすくなるのです。
孤独を和らげるためには、安心してつながれる場や支援を知ることも大切です。
詳しくは「あなたはひとりじゃない|内閣府 孤独・孤立対策推進室」で、支援制度や取り組みが紹介されています。
10. 心身のコンディションの乱れが生きづらさを引き起こす
体の調子は心の状態と密接につながっています。
睡眠不足や慢性的な疲れ、ホルモンバランスの乱れは、気持ちの余裕を奪い、些細な出来事でも大きな負担に感じやすくなります。
「ただ休めばいいのに休めない」
「眠っても疲れが取れない」
そんな状況が続けば、心の防御力は低下し、生きづらさを強く感じるようになります。
心身のコンディションを整えることは、生きづらさを和らげるために欠かせない要素なのです。
11. 遺伝や生まれ持った気質が関わる生きづらさ
生きづらさの背景には、遺伝や生まれ持った気質が関わっていることがあります。
人の脳や神経の働きには個性があり、刺激に敏感であったり、不安を感じやすかったりする特性は、ある程度「持って生まれたもの」と考えられています。
これは「変えられないから仕方ない」という意味ではありません。
むしろ、生まれ持った特徴を理解することで「だから自分はこう感じやすいのだ」と納得でき、自分を責めずにすむようになります。
たとえば、HSP(Highly Sensitive Person)のように感受性が強い人は、小さな音や光、人の表情に敏感に反応します。
同じ状況でも他の人より疲れやすいのは「弱いから」ではなく、「敏感さという気質」を持っているからです。
「自分は生まれつきこういう傾向がある」と受け止めることは、生きづらさを個性として理解し直す第一歩になります。
【一緒に読みたい記事】
生きづらさと病気・発達特性とのちがい

生きづらさを抱えていると、「これは病気なのだろうか」「発達障害なのではないか」と不安になる人が少なくありません。
しかし、生きづらさは必ずしも診断が必要な状態とは限らず、誰もが人生の中で自然に感じることがある心の反応です。
ここでは、病気や発達特性とのちがいをやさしく整理しながら、安心できる視点をお伝えします。
1. 生きづらさは「診断が必要な状態」とは限らない
「生きづらい」と感じるからといって、必ずしも病気や障害があるわけではありません。
人は環境や状況によって強いストレスを受ければ、誰でも生きづらさを感じるものです。
たとえば、職場の人間関係で過度に緊張する、家庭環境で安心できない──こうした経験が重なれば、心が疲れて「生きづらい」と感じて当然です。
診断や治療が必要な場合もありますが、多くの場合は「状況と心の反応」が生きづらさをつくり出しているのです。
2. 病気や発達特性との境界をやさしく理解する
病気や発達特性は「専門家が診断基準に基づいて判断するもの」であり、自分ひとりで決められるものではありません。
一方、生きづらさは「診断の有無とは関係なく感じる心の状態」です。
たとえば、発達特性を持っている人は社会の中で強い生きづらさを抱えやすいですが、発達特性がなくても人間関係や働き方の影響で同じような悩みを感じることはあります。
大切なのは、「病気かどうか」を断定することではなく、今の自分がどう安心できるか を考える視点です。
3. 「普通の人でも生きづらさを感じる」安心感
生きづらさは特別なことではなく、多くの人が日常の中で経験するものです。
「自分だけがおかしいのではないか」と不安になる必要はありません。
たとえば、完璧を求めすぎる人、人に気を遣いすぎる人、未来への不安を抱える人──誰もが状況次第で生きづらさを感じます。
「誰にでも起こりうるもの」と理解するだけで、「自分は弱いから生きづらいのだ」という誤解から解放されやすくなります。
それは安心感を取り戻すための大切な一歩です。
生きづらさを感じやすい人の特徴

生きづらさは誰にでも起こりうるものですが、特に感じやすい人にはいくつかの共通点があります。
これらは「弱さ」ではなく、むしろ「感受性の豊かさ」や「真面目さ」が強く表れている特徴です。
ここでは代表的な特徴を整理してみましょう。
1. 自分を責めやすく完璧主義の傾向がある
「失敗してはいけない」「人に迷惑をかけてはいけない」という思いが強い人は、生きづらさを抱えやすいです。
小さなミスでも「自分はダメだ」と責めてしまい、心に余裕を持ちにくくなります。
たとえば、仕事で一度注意を受けただけで「もう信頼を失った」と思い込むことがあります。
これは責任感が強いからこそ起こる反応ですが、同時に心を追い込む原因にもなるのです。
2. 人混みや騒音に疲れやすい
人の多い場所や強い音、明るすぎる照明など、刺激が多い環境にいると極端に疲れてしまう人もいます。
これは感覚が敏感な人に多く見られる特徴で、外部からの情報を強く受け取るため、心身の負担が大きくなります。
たとえば、通勤電車で人の多さに圧倒されたり、ショッピングモールで長時間過ごすとぐったりしてしまうことです。
「体力がないから」ではなく、「刺激に敏感な特性」が原因であることを理解することが大切です。
3. 人の感情に強く影響を受けやすい
他人の気持ちに敏感すぎると、自分の感情まで引きずられてしまうことがあります。
誰かが不機嫌だと「自分が原因かもしれない」と思ったり、周囲の空気が重いと自分まで沈んでしまう。
これは「共感力が高い」という素晴らしい力の裏側でもあります。
しかし、その感受性が強すぎると、人の感情に振り回されてしまい、生きづらさを感じやすくなるのです。
たとえば、職場で上司の機嫌が悪いと自分まで緊張して疲れ果ててしまう──そんな経験はありませんか?
こうした特徴を持つ人は、決して「弱い」わけではなく、むしろ人一倍やさしさや感受性を備えています。
大切なのは、特徴を知ることで「だから自分はしんどかったんだ」と理解し、自分を責めずに過ごすことです。
生きづらさを放置するとどうなるのか

生きづらさを「気のせい」と思って我慢し続けてしまう人は少なくありません。
しかし、放置することで心と体に負担が積み重なり、日常生活に深刻な影響を及ぼすことがあります。
ここでは、生きづらさを放置したときに起こりやすい変化を整理してみましょう。
1. 自己否定が強まり心が弱りやすくなる
生きづらさを放置すると、「やっぱり自分が悪いのだ」と思い込みやすくなります。
それが繰り返されると、自己否定が深まり、心の回復力が弱まっていきます。
たとえば、仕事で少し注意されたときに「自分は何をやってもダメだ」と考えてしまうことです。
これは「失敗を学びに変える力」ではなく「失敗=存在の否定」へと直結してしまうため、心に大きなダメージを残します。
2. 人間関係や仕事で無理を重ねてしまう
生きづらさを抱えたまま無理に頑張り続けると、心と体の限界に気づきにくくなります。
「自分さえ我慢すればいい」と思うことで、仕事や家庭で必要以上に責任を背負い込みやすくなるのです。
たとえば、本当は疲れているのに残業を断れない、家庭で自分の気持ちを抑えて相手に合わせ続けてしまう。
その結果、ますます疲労が蓄積し、人間関係にも悪影響が及びやすくなります。
3. 孤独感や疲れが慢性化してしまう
生きづらさを誰にも話せずに抱え込むと、孤独感が強まり「自分だけが苦しい」と感じやすくなります。
さらに、無理を続けて心身が休まらない状態が続くと、疲れが慢性化してしまうこともあります。
たとえば、「休んでも休んだ気がしない」「人に会うのが億劫でますます孤立する」──そんな悪循環に陥ることもあります。
孤独と慢性的な疲労が重なることで、日常の小さなことさえ大きな負担になってしまうのです。
生きづらさは放置しても自然に消えるものではありません。
「気づいたときに小さな工夫を取り入れる」ことが、心を守り、悪循環から抜け出すための第一歩になります。
生きづらさの原因を理解したうえでできる心の整え方

生きづらさの原因を理解したあとは、少しずつ心を整えていくことが大切です。
大きく変わる必要はなく、むしろ「小さな工夫の積み重ね」が自分を守る力になります。
「今のままではダメ」と焦るのではなく、「今日できることを少し取り入れてみよう」と考えることで、心はゆるやかに楽になっていきます。
1. 原因を知って「自分を責めない」視点を持つ
生きづらさの原因が自分の弱さではなく、気質や環境に影響されていると知るだけで心は軽くなります。
「自分はダメだから苦しいのだ」と思うのと、「状況や特徴が重なってつらかったんだ」と理解するのとでは、感じ方がまったく違うのです。
たとえば、仕事で人一倍疲れてしまうのは努力不足ではなく、刺激に敏感な気質のためかもしれません。
それを理解すれば「弱い自分」ではなく「よく頑張ってきた自分」と見直すことができます。
責める視点をやめて、労わる視点を持つこと。それが生きづらさを和らげる第一歩です。
2. 小さなセルフケア習慣で心をゆるめる方法
生きづらさを抱えると「何から変えればいいのか」と戸惑いがちですが、必要なのは特別なことではありません。
日常の中に小さなセルフケアを取り入れるだけでも、心はゆるみやすくなります。
たとえば
- 深呼吸やストレッチで体のこわばりを解く
- 温かい飲み物をゆっくり味わう
- 数分だけスマホやSNSから離れる
こうした習慣を意識して積み重ねることで、「安心できる時間」が少しずつ増えていきます。
完璧に続けなくても構いません。大切なのは「やってみよう」と思えたときに、ほんの少し心をゆるめることです。
もっと気軽にセルフケアを取り入れたい方には「生きづらい人のためのセルフケア基本ガイド【無料】」もご用意しています。
安心を取り戻す小さな習慣をまとめたfeeveraの入門ガイドです。
3. 自然・静けさ・シンプルな暮らしから得られる安心感
人は自然や静けさに触れると、本能的に心が落ち着きやすくなります。
緑のある場所や静かな時間の中で過ごすことで、「何もしなくても大丈夫」という安心感が育まれます。
また、物や情報が多すぎる環境は心を疲れさせます。
余計なものを減らしたシンプルな暮らしは、気持ちをすっきりさせ、生きづらさをやわらげる土台になります。
「余白をつくること」が、自分をととのえる大切な習慣につながるのです。
4. 安心できる人やコミュニティに支えられる重要性
生きづらさを抱えると、「自分だけでなんとかしなきゃ」と思い込んでしまうことがあります。
しかし、人に頼ることは甘えではなく、自分を守るために必要な選択です。
安心できる人に気持ちを打ち明けるだけでも、心はぐっと軽くなります。
また、同じような悩みを持つ人とつながることは「自分はひとりじゃない」と感じられる大きな支えになります。
孤独の中で耐えるのではなく、寄り添える人や場所に少し身をゆだねること。
それが生きづらさを和らげ、心を安心へと導きます。
共感できる体験談から学ぶ「生きづらさの原因」と向き合うヒント

生きづらさに悩むとき、頭で理解するだけでは心は軽くなりにくいものです。
そんなとき、同じように苦しんできた人の体験談は、何よりも強い安心や共感を与えてくれます。
「自分もそうだったんだ」と語る声に触れることで、孤独ではないと知り、自分を受け入れるヒントが見えてきます。
1. 同じ悩みを抱える人が感じた「気づき」
「弱いから生きづらいのではなく、気質や環境の影響だったんだ」と気づいた瞬間、心がふっと軽くなった。
そんな体験を語る人は少なくありません。
たとえば、HSP気質による疲れやすさを「自分の努力不足」だと思い込んでいた人が、特徴を知ったことで「だから疲れて当然だった」と理解できた。
その気づきが、自己否定から解放されるきっかけになったのです。
人の気づきは、自分の視点をやさしく変えてくれる力を持っています。
2. 「自分だけじゃない」と思えることが心を軽くする
生きづらさに苦しんでいるとき、人は「こんなに苦しいのは自分だけだ」と感じがちです。
しかし、同じ悩みを共有する人の声を知ると、「自分だけじゃなかった」と思えるようになります。
それだけで心はすっと楽になり、「ありのままでもいいんだ」と安心できるのです。
たとえば、職場の人間関係で悩んでいるときに、同じような経験をした人の話を聞くだけで、「私も同じだ」と涙が出ることがあります。
共感は、心を支える大切なつながりです。
3. 完璧に解決しなくても「ととのえていく」視点の大切さ
生きづらさは一気に消え去るものではありません。
むしろ「完全に解決しなければ」と思うほど、心は追い込まれてしまいます。
大切なのは「一度で治す」ことではなく、「少しずつととのえていく」ことです。
たとえば、疲れたときに深呼吸をする、安心できる音楽を聴く、自然に触れる時間をつくる。
小さな工夫を積み重ねることで、心はゆるやかに落ち着きを取り戻していきます。
「ととのえながら生きていく」という視点があるだけで、完璧を求めなくてもよい安心感が広がります。
今日から始められる小さな第一歩

生きづらさを一気に解決することは難しいですが、今日からできる小さな行動はあります。
「大きく変わらなければ」と焦る必要はありません。
むしろ、ちいさな一歩が心をゆるめ、安心感を育てるきっかけになります。
1. 深呼吸や自然音に意識を向けてみる
一日の中で数回、意識して深呼吸をするだけでも心は少し落ち着きます。
呼吸に集中することで頭の中のざわめきが静まり、安心感を取り戻しやすくなるのです。
さらに、自然音──小鳥の声や雨音、川のせせらぎ──に耳を傾けることも効果的です。
「自然に包まれている」と感じる時間は、心を緩める小さな休息になります。
もちろん「そんな簡単なことで生きづらさが軽くなるなら苦労しない」と思う人もいるでしょう。
それはとても自然な感覚ですし、実際に大きな悩みや疲れが一瞬で消えるわけではありません。
けれども、小さな習慣は“重荷を全部なくす”のではなく、“心の負担を少し軽くする”ことに意味があります。
たとえば深呼吸をしたあと、ほんの数十秒でも「少し楽になったかも」と感じられたなら、それは確かに生きづらさを和らげる第一歩なのです。
深呼吸をもっと効果的に取り入れたい方は、「リラックスする呼吸法でストレス解消!簡単な実践ガイド」もあわせてご覧ください。
2. スマホを置いて「静かな時間」を3分つくる
情報や刺激が多すぎると、心はどんどん疲れていきます。
そのため、短い時間でもスマホを手放し、静かな時間を過ごすことが大切です。
たとえば、寝る前の3分だけスマホを置き、明かりを落として目を閉じる。
それだけでも「心を休ませる余白」が生まれます。
「たった3分ならできそう」と思えるくらい小さな習慣から始めてみましょう。
3. 気持ちをノートに書いて自分を整理する
頭の中にモヤモヤが渦巻いていると、生きづらさはさらに強まります。
そんなときは、気持ちをノートに書き出してみるのがおすすめです。
書くことで心の中にある感情が整理され、「自分はこう感じていたんだ」と客観的に気づけます。
「ネガティブな言葉ばかり書いてしまった」としても、それで構いません。
心の中を外に出すこと自体が、安心につながります。
今日からできる小さな第一歩は、派手なことや特別な方法ではありません。
深呼吸・静かな時間・書き出すこと──この3つの習慣は、誰でも無理なく取り入れられます。
大切なのは「続けること」ではなく、「試してみよう」と思えた瞬間に実行することです。
体験談|「生きづらさ」と向き合ってきた私の歩み
ここでは、自身が経験してきた「生きづらさ」の背景をお話しします。
同じような悩みを抱える人が「自分だけじゃない」と思えるきっかけになればうれしいです。
1. 幼い頃から積み重なった家庭環境の影響
わたしの生きづらさは、家庭環境・体調・メンタル面が重なったところにあります。
生まれてすぐ母が離婚し、母の顔を見たことはありません。
父とその祖父母の家庭で育ちましたが、父は小学生のころから引きこもりがちになり、家族内の喧嘩も時折ありました。
祖母は昔ながらの価値観を持っており、アニメや漫画に否定的だったり、派手な服を禁止したりと、抑圧的な雰囲気がありました。
わたしは常に気を使うことが多く、それは進路選択にも影響しました。
2. 進路の壁と家族の変化が与えた衝撃
特別裕福な家庭ではなく、祖母からは「進学には失敗がある」と反対されました。
父は機能しておらず、高校三年生の進路決定期には自らの事故で腕を失い、その知らせを聞いた私は大きなショックを受けました。
この頃にはストレスを受けやすい体質で、常に眠気やだるさ、緊張感を抱え、公務員試験に合格したものの、身体と精神が限界でスタートできませんでした。
社会のスタート地点から「生きる意味」を失ったように感じていました。
3. 札幌での暮らしと「生きづらさ」との共存
その後、家を出る決意をし、札幌で暮らし始めて10年が経ちました。
生きづらさは札幌に来てからも抱え続け、生活にも苦労しましたが、それでも何度もくじけながら今日まで生きてきました。
生真面目で責任感が強い性格は、遺伝や気質によるものかもしれません。
体調は悪くなっていきましたが、「適当さ」や「肩が軽くなる考え方」、セルフケアの基本を少しずつ取り入れながら、生きづらい部分を和らげてきました。
4. 支えを受け入れることで見えた光
人生は流れるままに進んでいますが、生きることさえあきらめなければ何とか生活できています。
孤独でどうしようもなくなったとき、「自分だけでどうにかしよう」とする必要はありません。
自分の軸を持つことは大切ですが、誰かの支えを受けることは恥ずかしいことではない。
そう思えるようになったとき、わたしの中で生きづらさの重さがほんの少し軽くなりました。
まとめ
生きづらさの原因を知ることは、心を軽くする大切な一歩です。
気質や環境、過去の体験や社会のプレッシャーなど、多くの要因が重なって生きづらさは生まれます。
決して「自分が弱いから」ではなく、背景を理解することで自己否定から少しずつ解放されていきます。
自分を責めるよりも、「ここまでよく頑張ってきた」と認める視点を持つこと。
深呼吸や静かな時間、安心できる人とのつながりなど、小さなセルフケアを積み重ねることが回復の道につながります。
生きづらさは誰もが感じる自然な心の反応です。
「一人で抱え込まなくていい」と知るだけで、歩みはやわらかくなります。
今日からできる小さな一歩を、自分にやさしく取り入れてみましょう。

私は機能不全家族のもとに育ち、人との関わりにストレスを感じやすく、常に体調不良を抱えるような「生きづらさ」を経験してきました。その経験からメンタルヘルスに強く関心を持ち、同じように苦しむ人の役に立ちたいと考えるようになりました。
最初の取り組みは「心地よさ」をテーマにした天然竹ヘアブラシの販売。そこから歩みを進め、現在は feevera(フィーヴェラ) という、生きづらさを抱える人に向けてセルフケアを届けるブランドを運営しています。
心理カウンセラー資格を活かしながら、
五感にやさしいセルフケア
心がふっと軽くなる生き方のヒント
繊細さを否定しない暮らしの提案
を発信し、少しでも「安心できる時間」を届けられるよう活動しています。