最終更新日:2025.10.22
「また、今日もイライラしてしまった……。」
帰り道でそんなふうに小さくため息をついた経験はありませんか。
本当は穏やかに過ごしたいのに、ちょっとした言葉や出来事に心が揺れてしまう。
相手を責めたいわけでもないのに、イライラした自分に落ち込んで、「HSPのくせに優しくなれない」と自分を責めてしまう——。
実は、HSPがイライラしやすいのは特別なことではありません。
繊細な神経が疲れすぎているとき、脳は“もう限界だよ”というサインを出しているのです。
つまりイライラは「弱さ」ではなく、「心が休みを求めている証」。
この記事では、HSPがイライラしやすい理由をわかりやすく解説し、心をやさしく整えるための具体的なセルフケア方法を紹介します。
「どうしてこんなに疲れるんだろう」と感じているあなたが、少しでも安心して自分にやさしくなれるように。
ここから、穏やかさを取り戻すためのヒントをお届けします。
もし「HSPってどんな特徴があるんだろう?」と感じた方は、こちらの記事でやさしく解説しています。
繊細さは、あなたの中にある“感じ取る力”。
その特性を理解することで、イライラや生きづらさも少しずつ軽くなっていきます。
HSPはなぜイライラしやすいの?繊細な心のメカニズムを理解しよう

生まれつき感受性が高いHSPは、外の刺激や他人の感情を強く受け取りやすいため、心が疲れやすく、ふとした瞬間にイライラを感じやすくなります。
これは性格の欠点ではなく、繊細な神経が一生懸命あなたを守ろうとしている反応です。
まずは「なぜイライラしやすいのか」を理解することから、心をととのえる一歩が始まります。
1. HSP(繊細さん)とは?感受性が強い人の特徴をやさしく解説
HSPとは、Highly Sensitive Person(ハイリー・センシティブ・パーソン)の略で、他人よりも深く感じ取り、細かい変化に気づく気質を持つ人のことです。
たとえば
- 人の表情や声のトーンから感情を読み取ってしまう
- にぎやかな場所で疲れやすい
- ちょっとした出来事を何度も思い出してしまう
そんな特徴に心当たりがある人は、感受性の高さゆえに心のキャパシティを超えてしまうことがあるのです。
つまり「繊細さ」は弱さではなく、“深く感じ取る力”の表れです。
2. HSPがイライラしやすいと言われる3つの心理的・生理的な理由
HSPがイライラを感じやすいのは、心の仕組みと体の反応が深く関係しています。
- 感覚の過敏さ
音・光・においなどの刺激を強く感じ、脳が疲れやすい。 - 共感性の高さ
相手の気持ちを自分のことのように受け取り、心が緊張しやすい。 - 理想の高さと自己責任感
「ちゃんとしなきゃ」と自分を追い込んでしまう。
どれも“よく感じ取れる力”が関係しています。
だからこそ、疲れやすさやイライラは“感じすぎるやさしさのサイン”なのです。
3. 怒りっぽいわけじゃない。HSPの「イライラ」は心のSOSサイン
HSPのイライラは、「我慢の限界」や「心が疲れすぎているよ」というSOSです。
たとえば、
- 小さな音や言葉に過剰に反応してしまう
- 誰かの態度に必要以上に傷つく
- 自分を守れなかったことに自己嫌悪する
これらは、怒りというより“心が悲鳴を上げている状態”です。
イライラは悪いことではなく、「今は少し休もう」という合図。
そう気づけるだけで、心は少し軽くなります。
4. HSPが感じやすい刺激(音・人間関係・環境)の影響とは
HSPは、五感や人間関係の刺激を強く感じるため、環境の影響を大きく受けます。
- 人混みや大きな音に疲れる
- 他人の感情や空気の変化に敏感
- 部屋の乱れや明るすぎる照明に落ち着かない
これらの刺激が積み重なることで、神経が過敏になりイライラしやすくなります。
静けさ・自然・やわらかい光など、“心がほっとできる環境”を意識することが、HSPが自分を守るうえでとても大切です。
このように、HSPのイライラは「感受性の高さ」と深くつながっています。
自分を責めるのではなく、「心ががんばっている証拠」だと受け止めてみてください。
HSPがイライラしやすいときに起こりやすい5つのパターン

HSPのイライラには、「特定の状況で繰り返し起こりやすいパターン」があります。
それを知ることで、「あ、自分はこの状態かも」と客観的に気づけるようになり、心を守るための小さな対策が立てやすくなります。
ここでは、HSPが特にイライラしやすくなる5つの場面を、やさしく紐解いていきます。
1. 職場や家庭など「人間関係」で起こるHSPのイライラ
HSPのイライラの多くは、人との関わりの中で生まれます。
なぜなら、HSPは相手の表情や声のトーン、ちょっとした間の取り方などから、相手の感情を深く読み取ってしまうからです。
たとえば
- 職場で上司の機嫌が悪いと、自分が原因かもと思って落ち込む
- 家族やパートナーの言葉を必要以上に気にしてしまう
- 相手に嫌われないように、つい我慢してしまう
こうした積み重ねが続くと、心の中で小さな不安や緊張が溜まり、やがて“イライラ”という形で表に出てしまいます。
他人との関係に疲れたときは、距離をとる勇気もセルフケアの一つです。
「少し静かな時間を持つことは、逃げではなく、自分を守る選択」だと覚えておいてください。
2. 感情を我慢しすぎて「限界」で爆発してしまうとき
HSPは人に気を使うあまり、怒りや不満を抑え込みがちです。
「嫌な気持ちを出したら、相手を傷つけてしまうかも」と思い、感情を飲み込むことで人間関係を守ろうとします。
しかし、我慢を続けるほど心の負担は大きくなり、ある瞬間に「もう無理!」と限界を迎えてしまうことがあります。
そのとき、急に涙が出たり、些細なことで強く反応してしまったりして、「どうしてこんなにイライラしてしまうんだろう」と自己嫌悪に陥る人も少なくありません。
けれど、それは弱さではなく、ずっと我慢してきた優しさの結果です。
心の中に溜め込んだエネルギーが“これ以上は無理”と知らせているだけ。
感情を抑え込むよりも、少しずつ「疲れている」「つらかった」と言葉にしていくことで、心は穏やかさを取り戻していきます。
3. 他人の気持ちを優先しすぎて疲れる「共感疲労」
HSPは、他人の悲しみや不安を自分のことのように感じ取る「共感力の高さ」を持っています。
それは人に寄り添う力でもありますが、同時に「共感疲労」を招く原因にもなります。
たとえば
- 同僚や友人の悩みを聞いて、自分まで苦しくなる
- SNSのニュースを見て、心がざわついて眠れない
- 誰かが怒られていると、自分も胸が痛くなる
共感しすぎることで心のバランスが崩れ、「なんでこんなに疲れるんだろう」と自分を責めてしまうこともあります。
でも本当は、あなたの心がそれだけ“やさしさに満ちている”ということ。
だからこそ、他人の感情を受け取りすぎないために、「聞いた話を一度“外に出す”」習慣をつくってみてください。
たとえば、ノートに書き出したり、自然の中を散歩したり。
心の中に残ったものをそっと手放すだけでも、ずいぶん軽くなります。
【一緒に読みたい記事】
4. 「完璧にやらなきゃ」と思うほど苦しくなる理想主義
HSPの人は、責任感が強く、何事も丁寧にやり遂げたいという誠実さを持っています。
しかし、その誠実さが「完璧主義」に変わると、小さなミスや思い通りにいかない出来事に対して強いストレスを感じてしまいます。
「もっとちゃんとしなきゃ」「まだ足りない」と自分を追い込み、理想と現実のギャップにイライラしてしまう。
たとえば
- 仕事で少しのミスを何度も思い出す
- 家事や育児がうまくいかず、自分を責めてしまう
- 他人の評価に左右されやすい
でも本当は、「完璧にしよう」としている時点で、すでに十分に頑張っています。
HSPの丁寧さは、まわりに安心やあたたかさを与えているということを忘れないでください。
少し肩の力を抜いて、「まあいいか」とつぶやけた日が、心が整いはじめる最初の一歩です。
5. 体調・ホルモンバランス・睡眠不足など身体要因によるイライラ
HSPの心の揺らぎは、実は体調とも深く関係しています。
睡眠不足、ホルモンバランスの変化、低気圧、冷え、空腹――
これらの小さな身体の不調が、神経を敏感にし、イライラを引き起こしやすくします。
特にHSPは身体感覚にも敏感なので、「心の問題」ではなく「体がSOSを出している状態」であることも少なくありません。
たとえば
- 生理前や季節の変わり目に、情緒が不安定になる
- 寝不足が続くと、思考がネガティブに傾く
- 食事を抜くと、集中できず感情が揺れやすい
イライラを感じたとき、「私は今、体も疲れているのかも」と気づくだけで、心の負担はやわらぎます。
お茶を飲んだり、温かいお風呂に入ったり、“自分の身体に優しくする時間”を意識的にとることが、心をととのえるための大切なセルフケアです。
イライラの背景には、必ず「がんばりすぎた自分」がいます。
自分を責めるのではなく、「私、よく頑張ってるね」と声をかけてあげること。
その一言が、HSPの心をそっとやわらげてくれます。
HSPのイライラをやさしく整える5つのセルフケア習慣

HSPが感じるイライラは、心が疲れているときに自然と出てくる反応です。
だからこそ、無理に「消そう」とするよりも、やさしく「整える」ことが大切です。
ここでは、心を穏やかに戻すためのセルフケアを5つご紹介します。
どれもすぐに試せて、日常の中で少しずつ心を回復させてくれる方法です。
1. 「疲れた」と感じたら刺激を減らす(照明・音・スマホ)
イライラを感じたときは、まず外からの刺激を減らすことが一番の近道です。
HSPの脳は常に多くの情報を受け取っており、音や光、通知音といった刺激が重なるほど、神経が疲れて感情のバランスを保ちにくくなります。
照明をやわらかくしたり、テレビやスマホの音を少し下げたりするだけでも、心は静かさを取り戻していきます。
たとえば
- 部屋の明かりを間接照明に変える
- スマホを30分だけ「おやすみモード」にする
- お気に入りの静かな音楽を流す
こうした小さな工夫が、「もう大丈夫」と感じられる心の余白を作ります。
心が疲れたときは、暮らしを少しシンプルにしてあげるだけでも、驚くほど気持ちが軽くなることがあります。
物や情報を減らし、静けさを取り戻す工夫をまとめています。
2. 「私は今、疲れているだけ」と気づくセルフリフレーミング
イライラを感じた瞬間に、「私ってダメだな」と自分を責めてしまう人は少なくありません。
でも、その感情の多くは“怒り”ではなく“疲れ”です。
HSPの脳は他人の表情や言葉を敏感に受け取り続けているため、気づかないうちにエネルギーを使い切ってしまうことがあります。
そんなときは、
「私は今、疲れているだけ」
「悪いのは私じゃなくて、心のエネルギー残量」
と、心の中でやさしく言葉をかけてあげてください。
この“セルフリフレーミング(考えの切り替え)”ができると、イライラの根を深くしないまま、心が静かに落ち着いていきます。
【一緒に読みたい記事】
3. イライラの裏にある本音を書き出して、心を整理する
HSPのイライラの裏には、ほとんどの場合「本当の気持ち」が隠れています。
たとえば、「理解してもらえなかった悲しみ」や「報われないつらさ」など。
それを無視すると、心の中で小さなもやもやが積み重なっていきます。
ノートやスマホのメモに、思ったままの言葉を書き出してみましょう。
誰に見せるわけでもないので、きれいな言葉でなくて大丈夫です。
- 本当は寂しかった
- あの言葉がずっと引っかかっていた
- 私ばっかり頑張ってる気がする
そうして言葉にすることで、頭の中の絡まった糸が少しずつほどけていきます。
書き終えたあと、静かに深呼吸をするだけで、心は少し軽くなります。
【一緒に読みたい記事】
4. 香り・呼吸・ぬくもりで神経を落ち着ける(五感ケア)
HSPは感覚が鋭い分、「五感を整えるケア」がとても効果的です。
特に香り・呼吸・ぬくもりの3つは、直接神経をやさしく落ち着かせてくれます。
たとえば
- お気に入りのアロマを焚く
- 温かいお茶を両手で包み、ゆっくり深呼吸する
- 湯船に浸かって、体の芯から温める
こうした行為は、「今ここ」に意識を戻す手助けになります。
感情が波立つときこそ、思考よりも感覚を使って整えることが大切です。
「心が落ち着く香り」や「好きな手触り」を見つけるのも、自分を理解するやさしい習慣のひとつになります。
香りは、心を整えるうえでとても頼もしい味方です。
アロマの香りを通して「安心できる空気」をつくるだけで、心の緊張がふっとほどけることがあります。
香りの選び方や楽しみ方を、やさしくまとめています。
5. 「完璧じゃなくていい」と思える“自分への声かけ”を習慣に
HSPは真面目で努力家な人が多く、「もっと頑張らなきゃ」「ちゃんとしなきゃ」と自分を追い込みやすい傾向があります。
その気持ちは素晴らしいものですが、いつのまにか「完璧でない自分=価値がない」と感じてしまうこともあります。
そんなときは、自分にやさしく声をかけてみてください。
- 「今日はここまでできたら十分」
- 「うまくできなくても大丈夫」
- 「私は頑張ってる」
このような言葉は、心の中に“小さな安心”を灯してくれます。
完璧を目指すよりも、心が穏やかでいられることを優先するほうが、長い目で見て本当の意味での「ととのう」につながります。
考え方を少し変えるだけで、毎日がもう少し優しく見えてきます。
イライラを整えるというのは、感情を抑えることではありません。
心が乱れたとき、そっと自分に優しくしてあげる時間を持つこと。
それがHSPにとっての“回復”であり、“強さ”でもあります。
イライラする自分を責めないために大切な考え方

HSPは、怒りやイライラを感じたあとに「こんな自分、嫌だな」と自己嫌悪に陥りやすい傾向があります。
けれど、イライラは悪いことでも未熟さでもありません。
それは、あなたの心が“もう限界だよ”と伝えてくれているサインです。
ここでは、イライラした自分を否定せず、やさしく受け止めていくための考え方をお伝えします。
1. 「イライラ=悪」ではなく、心が守ろうとする自然な反応
イライラという感情は、あなたの心が「これ以上は無理」と伝える防御反応です。
たとえば、強い光を浴びたときに目を閉じるように、心もまた、ストレスを受けすぎたときに「イライラ」という形で自分を守ろうとします。
「怒っちゃダメ」「優しくいなきゃ」と思い続けると、心の負担はどんどん大きくなります。
だからこそ、まずは「イライラして当然」と思ってください。
その感情は、あなたがちゃんと感じ取れている証であり、感情を押し殺さずに生きている証拠です。
2. 感情を抑えず、“やさしく受け止める”姿勢が回復を早める
HSPは「我慢」や「抑える」ことが得意ですが、感情は抑えるほど強くなります。
それよりも、出てきた感情をそのまま認めてあげることが回復の第一歩です。
「イライラしてるね」
「今日は余裕がないんだね」
そんなふうに、自分の中の声にやさしく気づいてあげてください。
感情を否定せずに見つめるだけで、心の緊張がゆるみ、落ち着きを取り戻していきます。
たとえば、静かな部屋で深呼吸をしながら「大丈夫、今は感じていい時間」とつぶやくと、その言葉が自分へのやさしい手当てになります。
3. 怒りの裏にある「悲しみ・不安・疲れ」を理解する
イライラの奥には、たいてい“本当の気持ち”が隠れています。
HSPのイライラは、実は「悲しみ」や「不安」、「わかってもらえなかった寂しさ」からくることが多いのです。
たとえば、
- 自分の努力が伝わらず、悲しかった
- 人に頼れなくて、心細かった
- 休みたいのに、休むことに罪悪感があった
そんな感情を見つめてあげると、怒りは少しずつやわらぎます。
「怒り」は悪者ではなく、“心が本音に気づいてほしい”というサイン。
イライラの下にある感情を優しくすくい上げることが、HSPにとって最も大切なセルフケアです。
4. HSPの繊細さは“弱さ”ではなく、“人に寄り添う力”でもある
HSPの繊細さを「生きづらさ」と感じる人は多いですが、その感受性こそが、人の痛みを理解し、寄り添える力です。
イライラする自分を責めるのではなく、「自分は、それだけ心が動くほど誠実に生きている」と認めてみてください。
たとえば、誰かの言葉に傷つくのも、それだけ人の想いを真剣に受け取っている証拠です。
繊細であることは、決して弱さではなく、優しさの形です。
あなたのその感受性が、誰かを癒す力に変わっていく日がきっと来ます。
イライラを感じるのは、人間らしさのひとつ。
それを否定せず、静かに受け止めてあげることが、HSPの心をやわらげる大切なステップです。
HSPが穏やかに過ごすための暮らしの工夫

HSPが穏やかに過ごすためには、心が安心できる環境を意識的につくることが大切です。
どれだけ頑張っても、環境の刺激が強すぎると、心はすぐに疲れてしまいます。
逆に、静けさや自然の温もりを少し取り入れるだけで、驚くほど心が軽くなることがあります。
ここでは、HSPが日常を穏やかに過ごすための小さな工夫を紹介します。
1. 自然素材・香り・静けさを取り入れた「刺激を減らす暮らし」
HSPにとって、“静けさ”と“自然”は心の回復剤のようなものです。
強い光や人工的な音、化学的な香りなどの刺激は、知らないうちに神経を疲れさせます。
だからこそ、できる範囲で自然素材ややわらかな環境に変えてみましょう。
たとえば
- 木や竹、リネンなど自然素材のものを身の回りに置く
- お気に入りの香り(天然アロマ)で空間を整える
- 照明を暖色にして、静かな音楽を流す
こうした“感覚にやさしい空間づくり”は、HSPの心に穏やかさをもたらします。
自然の中に身を置くような時間を、日常の中にも少しだけ取り戻してみてください。
心が落ち着く空間は、何も特別なものでなくて大丈夫です。
素材や香り、明かりを少し整えるだけで、自分の部屋が“癒しのオアシス”へと変わっていきます。
あなたらしい“安心できる居場所”づくりのヒントを紹介しています。
2. SNSや情報のノイズを減らして心を休ませる時間をつくる
HSPは感受性が高いぶん、情報の受け取りすぎで疲れてしまうことがあります。
SNSやニュースを見ていると、他人の感情や社会の出来事まで自分の中に入ってきて、「なんだか落ち着かない」「心がザワザワする」と感じることもあるでしょう。
そんなときは、思い切って“情報の断食”をしてみてください。
- 夜はスマホをベッドの外に置く
- 通知を一時的にオフにする
- 休みの日はSNSを開かない時間をつくる
ほんの少しデジタルから離れるだけで、心の静けさが戻ってきます。
「誰かの世界」ではなく、「自分の世界」を生きる感覚を取り戻せる時間です。
3. 日常に“心をととのえる時間”を持つ(入浴・お茶・書く習慣)
忙しい毎日の中でも、HSPにとって大切なのは“心が落ち着く時間を意識的につくること”です。
完璧でなくてもいいので、毎日少しだけ「自分のための時間」を持つようにしましょう。
たとえば
- お風呂で照明を落として、ゆっくり湯に浸かる
- お気に入りの茶葉を丁寧に淹れて、香りを楽しむ
- 一日の出来事や感じたことをノートに書く
こうした時間は、心のバランスを整える“心のリセットボタン”になります。
「今日もよく頑張ったね」と、自分をやさしくねぎらう習慣を育てていきましょう。
4. イライラを感じた日の“リセットルーティン”を決めておく
HSPは、その日の出来事を引きずりやすく、夜になっても心が休まらないことがあります。
だからこそ、“心をリセットするルーティン”をあらかじめ決めておくことが大切です。
たとえば
- 夜は好きな香りのオイルでハンドマッサージをする
- 寝る前に「今日はここまでで大丈夫」と言葉にする
- 明かりを落とし、呼吸をゆっくり整える
そうすることで、「嫌なことがあった日=終わりのない不快感」ではなく、「整えて眠れる日」に変えることができます。
リセットルーティンを持つことは、HSPにとって“自分を守る術”です。
どんな日も、静けさを取り戻せる場所が自分の中にある——そう感じられるだけで心は強くなります。
気持ちの切り替えがうまくいかない日もあります。
そんなときは、モードを切り替える小さな習慣が、心の支えになります。
1日の終わりを“やさしく閉じる”ためのヒントをまとめています。
人に優しくしようとするあなたが、一番やさしくすべき相手は、ほかでもない“自分自身”です。
静けさに身を置き、香りやぬくもりに包まれる時間を少しでも増やすことで、心は自然と穏やかさを取り戻していきます。
イライラを溜めないためにできる日常の予防習慣

イライラは、ある日突然あふれ出るものではなく、“少しずつ積み重なっていく心の疲れ”が限界を迎えたときに表れます。
だからこそ、日々の暮らしの中で「溜めない工夫」をすることが、HSPにとって何よりのセルフケアになります。
ここでは、心を穏やかに保つために、今日からできる小さな予防習慣を紹介します。
1. 予定を詰め込みすぎない。余白を「心の休息時間」に
HSPは責任感が強く、頼まれると断れない傾向があります。
でも、スケジュールを詰め込みすぎると、知らないうちに心のキャパシティが限界を超えてしまいます。
1日の中に、何も予定を入れない「余白時間」を意識的に作りましょう。
たとえば
- 予定と予定の間に30分の休憩を入れる
- “やらなきゃ”と思ったことを1つ減らす
- 休日は「誰にも会わない日」をつくる
この“余白”が、HSPの心を守るバリアになります。
ゆるやかな時間があるだけで、イライラの芽は小さなうちに鎮まります。
2. 人の機嫌や感情を「自分の責任」と思わない
HSPは相手の表情や言葉に敏感で、「私のせいかも」と感じやすい特徴があります。
しかし、他人の機嫌や感情は、その人自身の問題であり、あなたの責任ではありません。
誰かが不機嫌でも、「今、あの人はあの人の世界で起きていることを感じているだけ」と、心の中でそっと切り離してみてください。
たとえば
- 相手の反応を“自分の評価”と結びつけない
- 人の問題と自分の問題を区別する
- 「私は私、相手は相手」と心の中で繰り返す
この意識の切り替えが、イライラの予防にも大きく役立ちます。
他人の感情を全部受け取らなくていい。
あなたは、あなたの心を守っていいのです。
3. 小さな“安心ルーティン”を持っておく
HSPにとって、日常の中に“決まった安心”があることはとても大切です。
毎日の終わりや朝の始まりに、自分を整えるルーティンを持っておくことで、感情の波が安定しやすくなります。
たとえば
- 朝、カーテンを開けて深呼吸する
- お気に入りのマグカップでお茶を飲む
- 夜、照明を落として静かな音楽を聴く
このような「心がホッとする習慣」を日常に散りばめることで、刺激を受けすぎた神経が自然と落ち着いていきます。
どんなに忙しくても、“自分をリセットする時間”を持つことが、イライラを防ぐいちばんの近道です。
安心できる習慣は、心を守る小さな“お守り”のようなものです。
「ちょっと休みたいな」と感じたときにできることを、いくつか見つけておくと安心です。
HSPが無理せず心を休めるための、やさしいアイデアをまとめています。
4. 感情を溜め込まない「小出しの発散」を意識する
イライラを溜め込む人ほど、「こんなことで怒るなんて…」と感情を押し込めがちです。
でも、感情は抑えるよりも、小出しに発散するほうが心にやさしいのです。
たとえば
- 紙に思ったことを自由に書き出す
- 軽い運動や散歩で体を動かす
- 信頼できる人に「ちょっと聞いて」と話す
大切なのは、“ため込む前に手放す”こと。
心の中に溜まった思いを、少しずつ外に出していくことで、HSPの繊細な神経は本来のやわらかさを取り戻していきます。
5. 「いい人」より「心が穏やかな人」でいる選択を
HSPの多くは、「いい人でいなきゃ」「嫌われたくない」と無意識に思っています。
でも、他人の期待に応え続けるほど、自分の心が削られてしまうこともあります。
“誰かにとってのいい人”ではなく、“自分にとって穏やかでいられる人”を選びましょう。
たとえば
- 気が進まない誘いは断ってもいい
- 自分のペースで動いていい
- 人の前で無理に笑わなくてもいい
そうやって少しずつ、自分を守る選択を重ねていくことが、イライラを溜めない生き方につながっていきます。
イライラを予防するコツは、「我慢しない」「抱え込まない」「早めに休む」の3つです。
HSPの繊細さは、無理をしないことで本来のやさしさに戻っていきます。
小さな安心を積み重ねながら、“いつもの自分”に戻れる暮らしを育てていきましょう。
【体験談】イライラを客観的に見つめられるようになった気づき
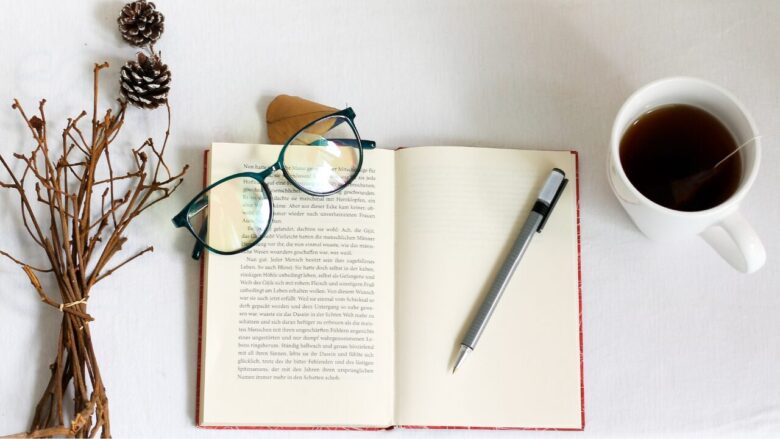
私は「イライラしない人」と見られることが多いですが、実際は人の言動によって心が揺れることがあります。
たとえば、責任のあるポストに就いたとき、同僚から「あなたは●●なんだからやらないといけないんだからね」と、言わなくてもいい一言を言われたことがありました。
その瞬間、「それは上長が言うことで、あなたに言われる筋合いはない」と心の中で反発してしまいました。
こうした職場の何気ないやりとりが、HSPにとっては大きなストレスになることもあります。
ただ、そこで感情をぶつけても状況は良くならないとわかっているので、私はまず深呼吸をして、少しその場を離れるようにしています。
そして、「相手は自分のためを思って言ってくれたのかもしれない」と感謝の視点を持つように心がけます。
さらに意識しているのは、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』に出てくる“スタンド”のように、自分の外側から客観的に状況を見ること。
自分や相手を少し離れた場所から見つめると、
「今は相手も焦っているだけかもしれない」
「自分も疲れているから敏感に反応しているのかもしれない」
と、冷静に判断できるようになります。
イライラしてしまう自分を責めずに、「なぜそう感じたのか」「何が心を刺激したのか」を整理すること。
そうすることで、感情に飲み込まれずに前へ進めるようになります。
また、普段から心にゆとりを作る習慣も意識しています。
感情は“器”のようなもので、いっぱいになるほど、少しの刺激であふれやすくなるからです。
だからこそ、日々の中で
- 深呼吸をする
- マインドフルネスで心を落ち着ける
- 信頼できる人に話を聞いてもらう
といった“感情を逃がす時間”を大切にしています。
イライラをゼロにするのではなく、「イライラしても大丈夫」と思える余白を持つことが、心をととのえる一歩だと感じています。
まとめ
HSPがイライラしやすいのは、心が繊細だからこそ。
人より多くの刺激を感じ取り、人の感情や空気に敏感に反応できるのは、あなたが「やさしく生きている証」です。
だからこそ、イライラを「悪いこと」として押し込める必要はありません。
それは、心が「もう無理をしないで」と伝えてくれている大切なサインです。
疲れたときは、照明を落として静かな時間を過ごす。
感情が乱れたときは、「私は今、疲れているだけ」と声をかける。
うまくいかない日には、「完璧じゃなくていい」と自分を抱きしめる。
そんな小さなセルフケアの積み重ねが、HSPの心をゆっくり整えてくれます。
feevera(フィーヴェラ)は、「頑張る」より「整える」という生き方を大切にしています。
イライラする自分を責めず、やさしく受け止めながら、少しずつ“心が安心できる暮らし”を取り戻していきましょう。
今日もあなたの中に、小さな静けさが芽生えますように。

家庭や人間関係の中で安心できず、生きづらさを抱えてきました。その経験から、心を守り整えることに目を向け、現在は feevera(フィーヴェラ)として、繊細さを否定しないセルフケアや、心が落ち着く生き方のヒントを届けています。
















