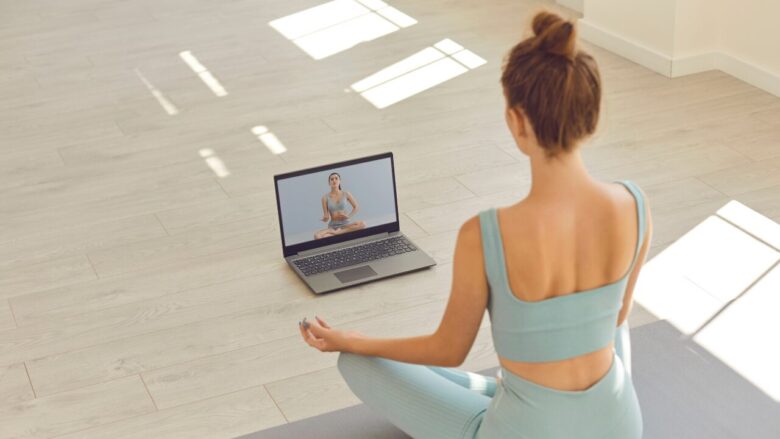最終更新日:2025.11.18
「涼しくなってきたのに、なんだか体が重い……。」
朝起きてもだるさが抜けず、気持ちまで沈んでしまう。
そんな不調を感じている人は、少なくありません。
それは、夏に溜まった疲れが秋になって表面化する“秋バテ”のサインかもしれません。
秋バテの時期は、8月下旬から10月頃にかけて起こりやすく、季節の変化に敏感な人ほど、自律神経のバランスを崩しやすくなります。
特にHSP気質の人は、気温差や環境の変化に強く反応し、心と体の両方がゆらぎやすい傾向があります。
「疲れやすいのは自分が弱いから」と責めてしまう方もいますが、それは自然な体の反応であり、休息を求めるサインです。
この記事では、秋バテの時期にあらわれる心身のサインや原因をわかりやすく解説し、季節の変わり目を穏やかに過ごすための“やさしい整え方”を紹介します。
「最近、なんとなく不調が続く」と感じているあなたへ。
少しずつ、自分をいたわる秋の過ごし方を見つけていきましょう。
【体験談】北海道の急な寒暖差に心も体もゆらいだ私の秋バテ
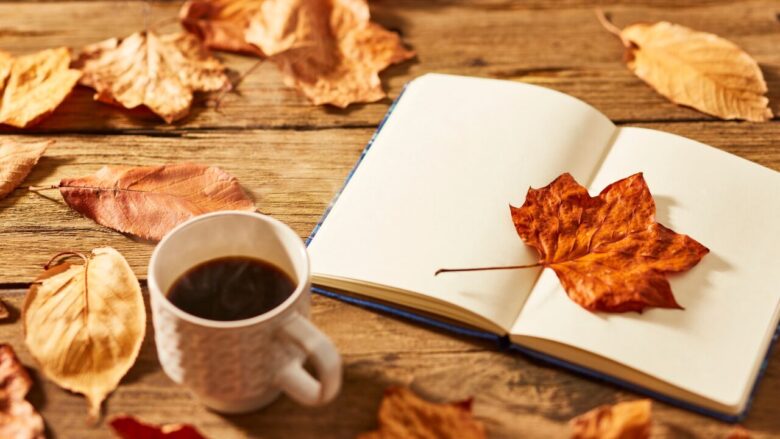
秋バテは、私にとって「毎年の風物詩」のように訪れます。
北海道に住んでいると、季節の変わり目がとても極端で、夏には30度を超える日が続いたかと思えば、秋になると一気に17度、10度と下がってしまう。
この急激な寒暖差のなかで、体は必死に温度調整をしようとします。
それだけでエネルギーをたくさん使ってしまい、普段よりもぐったりと疲れやすくなるのです。
気温がゆっくり下がってくれる地域なら、体も心も少しずつ季節に馴染んでいくのかもしれません。
でも北海道では、昨日暑かったのに今日突然冷える、
晴れていたと思ったら急に冷たい雨が降る、
秋だと思っていたら突然雪が舞い始める――。
そんな、めまぐるしい季節の変わり目が続くので、秋から冬にかけてはいつも天候に振り回されてばかりです。
昔の私は、ストーブ代がもったいなくて、少しくらい寒くても我慢して過ごしていました。
「まだ10月だから…」とつけるのを先延ばしにして気力で乗り切ろうとしていたのです。
でも、我慢するほど体調はどんどん悪くなって、手足は冷えきり、体力も気力も奪われ、毎年のように秋バテが長引いていきました。
今では、体の健康を優先するように変わりました。
寒い日には早めにストーブをつけて、体を冷やさないように意識しています。
あたたかさは“ぜいたく”ではなく、自律神経を守るための大切なケアだと気づいたからです。
北海道の家はとても乾燥しやすいので、ストーブをつけると空気がさらにパサパサになり、のどや鼻があっという間に痛くなってしまいます。
その小さな不調が積み重なると、ウイルスに負けやすくなり、結果的に風邪をひいてしまうことも少なくありません。
案の定、今年も例年どおり風邪を引きました。
気温差の大きい北海道では、毎年のように同じパターンがくり返されます。
だからこそ私は、
「秋バテは自分が弱いから起こるわけじゃない」
「体が季節の変化に必死についていこうとしているサインなんだ」
そう受け止められるようになりました。
季節に逆らわず、自分の体にやさしく寄り添うこと。
それが、秋バテと向き合ううえでいちばん大切な習慣だと、今では感じています。
秋バテとは?起こりやすい時期とその原因を知ろう

季節がゆっくりと移り変わる秋。
それなのに、体も心もついていけず、どこか不調を感じることはありませんか。
実は、その違和感は「秋バテ」と呼ばれる状態かもしれません。
秋バテは、夏にため込んだ疲れが秋になって表面化するもの。
体の冷えや気温差による自律神経の乱れが影響しています。
まずは、いつから秋バテが起こるのか、その時期と原因を知っていきましょう。
1. 秋バテはいつから起こる?ピークの時期と期間の目安
秋バテは、8月下旬から10月中旬ごろにかけて起こりやすくなります。
昼間は暑くても、朝晩は冷え込む時期。
この寒暖差が、自律神経に負担をかけてしまうのです。
たとえば、「朝は肌寒いのに日中は汗ばむ」「寝るときに冷えて眠りが浅い」など、体が温度調整を繰り返すことでエネルギーを消耗します。
そのため、秋の初めに疲れを感じるのは、自然な体の反応。
「まだ夏気分なのに、体がついていかない」と感じたら、それは秋バテのサインかもしれません。
【一緒に読みたい記事】
2. なぜ秋バテが起こるの?季節の変わり目に体がついていかない理由
秋バテの原因は、自律神経の乱れと冷えにあります。
夏の間、冷房や冷たい飲み物で体が冷え切ったまま、気温が下がる秋を迎えると、血流が悪くなりやすくなります。
また、朝晩の寒暖差が大きい秋は、体が何度も温度調整を行うため、知らないうちにエネルギーを使い果たしてしまうのです。
HSP気質の人は特に気候や環境の変化に敏感。
気圧の変化で頭痛や倦怠感を感じやすいこともあります。
「なぜこんなに疲れるのだろう」と感じるのは、あなたが弱いからではなく、敏感な感受性を持っているからです。
3. 夏バテとの違い|「秋」に特有のだるさの正体
夏バテは、真夏の暑さによって体力を消耗するもの。
一方で秋バテは、夏の疲れが抜けきらないまま、気温差に心身がついていけない状態です。
つまり、夏の疲れが「遅れて出てくる」のが秋バテ。
「最近ずっと眠い」「なんだか集中できない」と感じる人は多いでしょう。
体のエネルギーが不足し、心のエネルギーも下がってしまう。
それが、秋バテ特有の“抜けない疲れ”の正体です。
4. 秋バテが長引く人の特徴(気温・湿度・自律神経との関係)
秋バテが長引く人には、いくつかの共通点があります。
- 冷たい飲み物や食べ物を好む
- 冷房を長時間使う生活
- 睡眠リズムが乱れている
- 情報過多で頭が休まらない
- ストレスを感じても我慢してしまう
これらの習慣は、自律神経のバランスを乱し、回復を遅らせます。
特に、HSPの人は「人との関わり疲れ」も大きな原因に。
人の感情を受け取りやすいため、季節の疲れがさらに重なりやすいのです。
「なんで自分だけこんなに疲れるんだろう」
そう感じたときは、無理をしてきたサインかもしれません。
秋バテのサインに気づこう|体と心の症状チェック

秋バテは、体の疲れだけでなく、心の不調としてもあらわれます。
「最近なんとなく元気が出ない」「朝から気力が湧かない」――。
そんな小さな違和感も、秋バテのはじまりかもしれません。
体調が崩れる前に、心と体が発しているSOSに気づいてあげましょう。
早めに整えることで、秋のゆらぎをやさしく乗り越えられます。
1. 秋バテチェックリスト|自分の心と体の状態を確認しよう
秋バテの時期は、気づかないうちに心と体のバランスが崩れやすくなります。
「なんとなく不調だけど、理由がわからない」と感じるときは、一度立ち止まり、自分の状態をやさしく見つめてみましょう。
以下のチェックリストにいくつ当てはまるかを確認してみてください。
身体のサイン
- 朝起きても疲れが取れていない
- 頭痛や肩こりが続いている
- 食欲がわかない、または甘いものばかり食べたくなる
- 手足の冷えやむくみを感じる
- 寝つきが悪い、または夜中に何度も目が覚める
- 冷房の部屋に長くいるとだるくなる
- 胃腸の不調や便秘が気になる
心のサイン
- 気分が落ち込みやすくなっている
- 何をするにもやる気が出ない
- 小さなことでイライラしたり、涙が出やすい
- 人と話すのが少し重く感じる
- SNSやニュースを見たあと、心がざわつく
- 「休みたい」と思っても、罪悪感を感じてしまう
- 「何もしたくない」と感じる日が増えている
3つ以上当てはまった場合は、秋バテのサインが出ているかもしれません。
特に、HSP気質の人は季節の変化や気温差に敏感なため、「気のせい」と思っても、体が静かにSOSを出していることがあります。
無理に動こうとせず、まずは体を温めたり、睡眠のリズムを整えたりして、小さく「整える時間」を取り入れてみてください。
「秋バテに気づくこと」自体が、すでに回復への第一歩です。
自分を責めず、「今の自分を大切に扱う練習の時期なんだ」と受け止めていきましょう。
2. 身体にあらわれる秋バテの症状(だるさ・頭痛・食欲不振など)
秋バテの時期になると、体のあちこちに小さなサインが出てきます。
代表的なものは次の通りです。
- 朝起きてもだるさが取れない
- 頭痛や肩こりが長引く
- 食欲がなく、胃の重さを感じる
- 手足が冷える、むくみやすい
- めまいや立ちくらみが起こる
これらは、体温のコントロールや血流がうまくいかず、
エネルギーが消耗しているサインです。
特に、夏の冷房や冷たい飲み物で体の中が冷えていると、秋になっても体が回復しづらくなります。
「たいしたことない」と無理をしてしまうと、不調が長引く原因にもつながります。
「最近、朝がつらいな」「体が重いな」と感じたら、体が“休みたい”と伝えている合図かもしれません。
3. 心にあらわれる秋バテのサイン(やる気が出ない・落ち込みやすい)
秋バテは、心の不調としてもあらわれます。
気分の落ち込み、集中力の低下、やる気のなさ――。
それは決して「怠け」ではなく、自律神経が疲れてしまっているサインです。
秋は日照時間が短くなることで、「セロトニン(幸福ホルモン)」の分泌が減り、自然と気持ちが沈みやすくなります。
「なんとなく憂うつ」
「好きなことに手が伸びない」
そんなときは、心が静かに回復を求めているのです。
無理に元気を出そうとせず、まずは「いまの自分を責めない」ことから始めましょう。
4. HSP気質の人が秋バテを感じやすい理由
HSPの人は、季節や気温の変化にとても敏感です。
気圧・匂い・光・音といった外的な刺激に影響を受けやすく、その微妙な変化が、知らないうちにエネルギーを消耗させます。
また、周囲の感情や空気を感じ取りやすいHSPは、人間関係のストレスが重なりやすく、秋バテのような心身の疲れを強く感じやすい傾向があります。
「どうして自分だけ疲れやすいんだろう」
そう思うときもあるかもしれません。
けれど、それはあなたが“やさしい感受性”を持っているからこそ。
敏感さは欠点ではなく、心の豊かさの証でもあります。
5. 「怠け」ではなく自然な反応|自分を責めないために知っておきたいこと
秋バテの時期に何もしたくなくなるのは、体と心が「立ち止まる時間」を求めているからです。
疲れを感じるのは、怠けではなく、自然な回復反応。
無理に頑張り続けると、エネルギーはさらにすり減ってしまいます。
「今日は、何もできなくてもいい」
そうやって自分にやさしく声をかけるだけで、心の緊張がふっとゆるむことがあります。
休むことは、止まることではありません。
“これからまた歩き出すための準備”なのです。
feeveraが大切にしている「整える暮らし」は、そんな自分のペースを取り戻すための小さな習慣でもあります。
秋バテのサインは、誰にでも起こる自然なもの。
特に敏感でやさしい人ほど、体も心も繊細に反応します。
「しっかり休むこと」は、自分を守る大切な力です。
秋のゆらぎを感じたら、焦らず立ち止まり、“整える時間”を自分にプレゼントしてあげましょう。
秋バテの時期に実践したい“やさしい整え方”

秋バテを乗り越えるために大切なのは、がんばることではなく“整えること”。
「もっと動かなきゃ」と自分を追い立てるよりも、小さな習慣を一つずつ積み重ねるほうが、心と体は確実に回復していきます。
ここでは、秋バテの時期に心身をやさしく整えるための具体的な方法を紹介します。
1. 自律神経を整える3つの生活リズム(睡眠・食事・光)
秋バテの主な原因である自律神経の乱れを整えるには、「睡眠・食事・光」の3つのリズムを意識することが大切です。
- 朝はカーテンを開けて太陽の光を浴びる
太陽の光が体内時計をリセットし、1日のリズムを整えてくれます。 - 夜はスマホを早めに手放し、ぬるめのお風呂でリラックスする
画面の光は脳を覚醒させるため、眠りの質を下げてしまいます。
湯船に浸かり、体を温めるだけで副交感神経が優位になります。 - 一日三食をできるだけ同じ時間にとる
食事のリズムが整うと、血糖やホルモンのバランスが安定しやすくなります。
この3つのリズムを意識するだけで、体の中の“ゆらぎ”が整い、心も自然と穏やかになっていきます。
2. 体を温めて回復を促す|冷え対策と温活セルフケア
秋バテの時期は、知らないうちに体が冷えていることが多いです。
冷えは血流を滞らせ、だるさや疲れを悪化させる原因になります。
だからこそ、「体を温める」ことを意識してみてください。
たとえば、白湯を飲む、足首やお腹をカイロで温める、お風呂にゆっくり浸かる──それだけでも十分です。
温まった体は安心感を取り戻し、心までほっとやわらぎます。
「なんとなく元気が出ないな」と感じるときほど、やさしく体を温めてあげましょう。
冷え対策を続けることで、少しずつ心の緊張もゆるんでいきます。
もし、「どんなアイテムを使えばいいのか分からない」と感じたら、「冷え性対策グッズおすすめ10選|ぽかぽか快適に過ごせる!」の記事も参考にしてみてください。
あなたの体を、やさしく包み込むような“温活アイテム”がきっと見つかります。
3. 秋バテ対策におすすめの食材|根菜・きのこ・発酵食品
秋の旬の食材には、体を内側から温め、整える力があります。
特におすすめなのが、次の3つのグループです。
- 根菜類(にんじん・れんこん・さつまいも)
土の中で育った根菜は、体をじんわり温めてくれます。 - きのこ類(しいたけ・まいたけ・えのき)
免疫をサポートし、疲労感をやわらげるのに役立ちます。 - 発酵食品(味噌・納豆・甘酒)
腸を整えることで、心の安定にもつながります。
これらを少しずつ日々の食事に取り入れるだけで、体の中からエネルギーが戻ってくるのを感じられるでしょう。
「栄養で整えること」も、やさしいセルフケアのひとつです。
4. 疲れをためない暮らし方|スマホ・情報量を減らす習慣
現代の疲れの多くは、「情報の疲れ」でもあります。
HSP気質の人は特に、SNSやニュースなどの刺激に敏感で、心が休まりにくい傾向があります。
「少し疲れたな」と感じたときは、スマホを手放して、温かい飲み物をゆっくり飲む時間をつくってみてください。
情報を減らすと、呼吸が自然と深くなり、思考も静かになります。
何かを“増やす”より、“減らす”ことが、秋バテ対策の近道です。
5. 気分の落ち込みをやわらげる“心のセルフケア”習慣
秋バテの時期は、日照時間の減少や気温差で、心が沈みやすくなる季節でもあります。
そんなときは、無理に前向きになろうとしなくて大丈夫です。
代わりに、
- 心地よい音楽を聴く
- ゆっくり散歩する
- 好きな香りを取り入れる
こうした小さな“心の整え習慣”を取り入れてみましょう。
「癒されたい」と思う自分を受け入れることが、何よりのセルフケアです。
そしてもし、「もっと自分の心を整える方法を知りたい」と感じたら、生きづらい人のためのセルフケア基本ガイド【無料】 を読んでみてください。
feeveraが大切にしている“やさしく生きるためのセルフケア”を、日常の中で少しずつ実践できる内容になっています。
あなたのペースで、心をやわらげる時間を取り戻していきましょう。
6. 「何もしない時間」をつくる勇気|心を休める秋の過ごし方
私たちは「何かをしていないと落ち着かない」世界で生きています。
でも、心と体を整えるためには、“何もしない時間”こそ必要です。
予定を詰め込まず、ただ静かに過ごす時間をつくってみましょう。
ぼんやり空を見上げたり、温かいお茶を片手に深呼吸したり──。
そのひとときが、心を回復へと導きます。
「今日は、これでいい」
そう思える日が増えるほど、あなたの心は強くやわらかくなっていきます。
秋バテの時期に大切なのは、頑張ることではなく“整えること”。
生活リズムを見直し、体を温め、心をやさしく扱う。
そんな小さな積み重ねが、確実にあなたを軽くします。
疲れを感じたときこそ、「自分を大切に扱う練習の時間」だと思ってください。
feeveraが大切にしている「整える暮らし」は、どんな季節のゆらぎも受け入れながら、“心がやわらぐ日常”を取り戻すための一歩です。
秋バテを防ぐために、今からできる季節の準備

秋バテは、起こってから対処するよりも、「予防」こそが最もやさしいセルフケアです。
季節の変わり目は、体も心も変化に敏感になります。
だからこそ、「急に切り替える」のではなく、少しずつリズムを整えることで、秋の疲れを防ぐことができます。
ここでは、秋バテを防ぐために“今日から始められる”小さな準備を紹介します。
1. 季節の変化をゆるやかに受け入れる「生活リズム調整」
季節の移り変わりは、思っている以上に体に負担を与えます。
急な冷え込みや日の短さに、体がうまく対応できないと、自律神経が乱れて秋バテを招いてしまうのです。
そのために大切なのは、「ゆるやかに」変化を受け入れること。
- 就寝・起床の時間をできるだけ一定に保つ
- 朝の光を浴びて体内時計をリセットする
- 冷えを感じたら早めに上着を羽織る
このような小さな意識で、体が季節の変化についていきやすくなります。
HSP気質の人ほど気温や環境の変化に敏感です。
だからこそ、無理に“合わせよう”とせず、自分のペースで季節を迎えることが何よりの整え方です。
2. 冷房・服装・食事の切り替えポイント
秋のはじめは、まだ日中の暑さが残る時期。
ですが、夜や朝は冷え込むことが増え、体温の調整が難しくなります。
そんなときは、次の3つを意識するだけで、秋バテ予防になります。
- 冷房の設定温度を1~2℃上げて、体を冷やしすぎない
- カーディガンやブランケットを常備して、冷えを感じたらすぐ羽織る
- 冷たい飲み物を減らし、温かいスープや味噌汁を増やす
たったこれだけでも、体の温度リズムが整い、疲れにくく、心も落ち着きやすくなります。
秋バテの時期に不調を感じやすい人ほど、“体を冷やさない暮らし方”を心がけることが、最善のセルフケアです。
3. 秋を心地よく迎えるためのマインドセット
秋は、気温の変化だけでなく、心にも“ゆらぎ”が起こりやすい季節です。
そんなときに大切なのは、「頑張らなきゃ」より「整えよう」という気持ちを持つこと。
「やる気が出ない」「少し疲れた」と感じた日は、それを「自分を責める材料」ではなく、「心が休みを求めているサイン」と受け止めてあげましょう。
たとえば、
- 予定をひとつ減らして、早めに寝る
- 仕事帰りにお気に入りのカフェで温かい飲み物を飲む
- 夕方の空を眺めて、深呼吸する
こうした“小さなやさしさ”の積み重ねが、秋を穏やかに過ごす力になっていきます。
疲れを感じたときこそ、「いまは、やさしく生きる練習の時間」と思ってみてください。
秋バテの時期は、「頑張りすぎた体と心」が休息を求めているサインです。
季節の変化を受け入れ、冷えを防ぎ、心にゆとりを持つ。
それだけで、秋はもっとやさしく、あたたかい時間に変わります。
feevera(フィーヴェラ)が大切にしているのは、“整える暮らし”の中で自分を労わること。
あなたの秋が、少しでも穏やかで、「これでいい」と思える時間に包まれますように。
秋バテとどう向き合うか|“整える暮らし”を始めるために

秋バテを完全になくすことよりも、「ゆるやかに整える」という姿勢で向き合うことが大切です。
なぜなら、季節の変化に敏感な人ほど、無理に元気を出そうとすると、心も体もさらに疲れてしまうからです。
秋は“整えるための季節”。
焦らず、自分のペースで回復していくことで、心と体は少しずつ穏やかさを取り戻していきます。
1. 完全に治そうとしない|「整える」意識に切り替える
秋バテを「治さなきゃ」と思うと、知らず知らずのうちに自分を追い込んでしまいます。
本当に大切なのは、“治す”より“整える”という意識です。
整えるとは、
- 無理をせず、今の状態を受け入れること
- 小さな習慣を積み重ねて、バランスを戻していくことを意味します。
「今日は動けない」と感じる日があっても大丈夫です。
立ち止まる時間は、体が“回復のスイッチ”を入れている証。
焦らず、自分のペースで一歩ずつ整えていきましょう。
2. 1日のリズムをやさしく整える|朝・昼・夜の過ごし方
整える暮らしの基本は、「リズムを作ること」です。
自律神経は規則的な生活リズムで安定しやすくなります。
- 朝:カーテンを開けて太陽の光を浴びる
光を浴びることで体内時計がリセットされ、心も明るくなります。 - 昼:深呼吸を意識して、1日数回「息を整える時間」をつくる
忙しい日でも、数分の呼吸リセットで心のざわつきを減らせます。 - 夜:スマホやPCを早めに手放し、ぬるめのお風呂で温まる
光の刺激を減らし、体温をやさしく下げることで、深い眠りにつながります。
この3つのリズムを守るだけで、“秋バテの波”に飲み込まれにくくなり、心の余裕が戻ってきます。
3. 静けさを取り戻す時間をもつ|情報を減らして心を休める
現代の疲れの多くは、“情報疲れ”です。
HSP気質の人は特に、他人の感情やSNSの刺激に影響されやすく、気づかないうちに心が疲れてしまいます。
だからこそ、「何も見ない・聞かない時間」をあえてつくってみてください。
スマホを置いて、静かな音楽を流す。
温かい飲み物をゆっくり味わう。
それだけで、心の緊張がゆるみ、思考が整っていきます。
何かを“増やす”より、“減らす”ことで整う。
それが、feeveraが大切にしている“やさしい暮らし方”です。
4. 「できたこと」に目を向ける|小さな安心を積み重ねる
秋バテの時期は、「まだ十分にできていない」と感じやすくなります。
でも、整える暮らしにおいては、“できたこと”に目を向けることが何より大切です。
- 朝、窓を開けられた
- お茶をゆっくり飲めた
- 少し笑えた
――それだけで十分です。
小さな「できた」を積み重ねるたびに、心は確実に穏やかになっていきます。
「今日は、これでいい」
そう思える日が増えるほど、秋のゆらぎもやわらかく受け止められるようになります。
5. feeveraが伝えたい“整える暮らし”の本質
feevera(フィーヴェラ)が大切にしているのは、「がんばる生き方」ではなく「ととのえる暮らし」です。
疲れを感じたときは、“立ち止まっていい”というサイン。
やさしさや静けさを取り戻す時間こそ、本当の意味での“前進”です。
秋バテの時期は、あなたが「自分を大切に扱う練習」を始める絶好のタイミング。
心地よい光、あたたかい飲み物、静かな呼吸。
その一つひとつが、これからの季節を穏やかに過ごすためのやさしいお守りになります。
6. 季節にゆだねる力を育てる|“コントロールしない勇気”
秋のゆらぎを感じるとき、私たちはつい「どうにかしなきゃ」と思ってしまいます。
けれど、すべてをコントロールしようとするほど、心も体も緊張してしまいます。
季節の変化は、私たちの力ではどうにもできないことのひとつ。
だからこそ、“ゆだねる力”を育てることが大切です。
たとえば、
「今日は調子がいまいちだから、早めに休もう」
「少し寒いけど、温かい飲み物で整えよう」
――そんな小さな選択の積み重ねが、自然と自分を守る力になります。
「整える暮らし」は、がんばって完璧にするものではありません。
季節や気分の波に“逆らわずに寄り添うこと”こそ、やさしいセルフケアの始まりです。
焦らず、抗わず、いまの自分を受け入れる。
それが、feeveraが大切にしている“やさしく生きる力”です。
7. 私自身が感じた「秋バテとの向き合い方」
私も毎年、秋バテを感じています。
気温の変化に敏感な私は、秋口になると体の疲れをより強く感じ、昼間の眠気が増すのを実感します。
夏の疲れを引きずったまま、体が気温の変化に対応しようとするため、知らないうちにエネルギーを消耗しているのでしょう。
昔は秋口になると風邪を引いてばかりでしたが、「自分を大切にすること」を意識するようになってから、体調を崩すことが少なくなりました。
たとえば、
- あたたかい飲み物を飲むようにする
- 「まあいいか」と言ってストレスをためない
- 無理に頑張らないことを習慣にする
そんな小さな意識の積み重ねが、心にも体にも大きな変化をもたらしてくれます。
心と体はつながっています。
だからこそ、どちらか一方ではなく、両方を整えることが大切です。
常に医者がそばにいるわけではありません。
だから、自分の身を守り、自分を整える力こそが“セルフケアの基礎”になります。
季節の変わり目こそ、自分をいたわるタイミング。
焦らず、自分のペースで心を整えていきましょう。
秋バテを無理に克服しようとせず、「整えること」に意識を向けていく。
それが、HSPの繊細な心と体を守る最もやさしい方法です。
少しずつ、自分を大切に扱う日々を重ねていきましょう。
やがてその積み重ねが、“心が安らぐ暮らし”を育てていきます。
秋の疲れを感じやすい方は、「疲れがやばい?その原因と対処法を徹底解説」もぜひ参考にしてください。
まとめ
秋バテの時期は、心と体が「ゆっくり整えたい」と伝えている大切なサインです。
季節の変化に敏感な人ほど、自律神経や気持ちが揺れやすくなりますが、生活リズムを整えたり、体を温めたりするだけで、少しずつ回復へ向かうことができます。
「何もできない日があっても大丈夫」と受け入れることで、心の緊張はやわらぎます。
秋バテを無理に克服しようとせず、やさしく向き合う時間をつくってください。
ゆらぎの季節を、自分を責めるきっかけではなく、“自分をいたわる練習の季節”として過ごすことで、心と体はまた静かに整っていきます。

私は機能不全家族のもとに育ち、人との関わりにストレスを感じやすく、常に体調不良を抱えるような「生きづらさ」を経験してきました。その経験からメンタルヘルスに強く関心を持ち、同じように苦しむ人の役に立ちたいと考えるようになりました。
最初の取り組みは「心地よさ」をテーマにした天然竹ヘアブラシの販売。そこから歩みを進め、現在は feevera(フィーヴェラ) という、生きづらさを抱える人に向けてセルフケアを届けるブランドを運営しています。
心理カウンセラー資格を活かしながら、
五感にやさしいセルフケア
心がふっと軽くなる生き方のヒント
繊細さを否定しない暮らしの提案
を発信し、少しでも「安心できる時間」を届けられるよう活動しています。